弁護士とマッチングできます
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。

カスタマーハラスメントは、顧客の過度な要求・暴言・威圧的言動によって従業員の心身を疲弊させるだけでなく、企業の事業継続にも深刻な影響を与える社会問題のひとつです。
厚生労働省が2022年に提示したカスハラ対策マニュアルの公表以降、企業規模を問わず「顧客だから」という理由で不当な要求を受け入れてきた慣行を見直す動きが加速しています。
もしカスハラ対応で悩んでいるなら、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
弁護士なら、カスハラ加害者とのやり取りを代理してくれて早期解決が望めるほか、今後のカスハラ対策に関するアドバイスなども受けられます。
本記事では、カスハラの定義・対応策・予防策や、弁護士に相談・依頼するメリット、弁護士の選び方などを解説します。

ここでは「そもそもカスハラとは何か」「どのようなパターンやカテゴリーがあるのか」などについて解説します。
カスハラについては、厚生労働省が公表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」にて以下のように示されています。
顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの
カスタマーハラスメント対策企業マニュアルでは、カスハラについて顧客などからのクレーム・言動を広く射程範囲としています。
「顧客等」には、商品・サービスを利用した者・利用している者だけでなく、今後商品・サービスを利用する可能性がある潜在顧客も含むものとしています。
また、「当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らし、顧客が事業者などのサービスの提供主体に対して要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当であること」なども成立要件としています。
顧客などによる要求内容が著しく妥当性を欠く場合には、手段・態様に関わらず社会通念上不相当になる可能性が高いほか、要求内容の妥当性がある場合でも、手段・態様が悪質であれば社会通念上不相当と評価されうると考えられています。
ほかにも、「手段・態様により労働者の就業環境が害される」という害悪の存在についても定められています。
ここでの「就業環境への阻害性」とは、労働者が人格や尊厳を侵害する言動によって身体的・精神的に苦痛を与えられたことで就業環境が不快なものとなり、個人の能力の発揮に重大な悪影響があり就業環境として看過できない程度の支障が生じることを指すものとされます。
東京都産業労働局の「TOKYOノーカスハラ支援ナビ」によると、カスハラの代表的な行為類型は以下のとおりです。
|
ここでは、それぞれ具体的にどのような行為が該当するのか解説します。
まず、妥当性を欠く要求となるケースとしては以下のとおりです。
|
「就業者が提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合」とは、たとえば以下のような行為が該当します。
|
「要求内容が就業者の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合」とは、たとえば以下のような行為が該当します。
|
次に、違法または社会通念上不相当となる行為としては、以下のようなものが該当します。
|
身体的な攻撃とは、顧客が従業員に対して直接暴力を振るうなどして、身体的・精神的苦痛を与えることを指します。
一例として、以下のような行為が該当します。
|
精神的な攻撃とは、顧客が従業員に対して暴言や脅迫的な発言をするなどして、精神的苦痛を与えることを指します。
一例として、以下のような行為が該当します。
|
威圧的な言動とは、顧客が従業員に対して威圧的な態度を取るなどして、自分の要求を通そうとすることを指します。
一例として、以下のような行為が該当します。
|
謝罪の強要とは、顧客が従業員に対して過度な謝罪を強制することを指します。
一例として、以下のような行為が該当します。
|
執拗な(継続的な)言動とは、顧客が従業員に対して同じ内容の要求を繰り返すなどして、業務妨害や精神的苦痛を与えることを指します。
一例として、以下のような行為が該当します。
|
拘束する行動とは、顧客が従業員を時間的・物理的に拘束するなどして、業務妨害や精神的苦痛を与えることを指します。
一例として、以下のような行為が該当します。
|
差別的な言動とは、顧客が従業員に対して侮辱や不適切な発言をするなどして、精神的苦痛を与えることを指します。
一例として、以下のような言動が該当します。
|
性的な言動とは、顧客が従業員に対して性的な嫌がらせや不適切な言動をするなどして、精神的苦痛を与えることを指します。
一例として、以下のような言動が該当します。
|
個人への攻撃や嫌がらせとは、顧客が特定の従業員に対して中傷や批判をするなどして、精神的苦痛を与えることを指します。
一例として、以下のような言動が該当します。
|
最後に「要求内容の妥当性と、要求の実現のための手段・態様が違法または社会通念上不相当」となるケースとしては、以下のとおりです。
|
過度な商品交換の要求とは、たとえば以下のような行為が該当します。
|
過度な金銭補償の要求とは、たとえば以下のような行為が該当します。
|
過度な謝罪の要求とは、たとえば以下のような行為が該当します。
|
その他不可能な行為や抽象的な行為の要求とは、たとえば以下のような行為が該当します。
|
カスハラ問題に対する法整備は近年大きく進んでいます。
厚生労働省は、2022年2月にカスハラ対策企業マニュアルを策定し、企業が取るべき対応策を具体的に示しました。
カスハラ対策企業マニュアルでは、カスハラの定義・予防策・対応策などが包括的にカバーされており、企業の実務担当者にとって重要な指針となっています。
また、地方自治体でも対策が進んでおり、たとえば東京都では2023年10月に「カスタマーハラスメント防止対策推進事業」を開始し、企業向けの相談窓口の設置や啓発活動などをおこなっています。
ほかにも、東京都では2025年4月1日からカスハラ防止条例が施行されていたり、大阪府や愛知県などでも同様の取り組みが展開されていたりなど、全国的に対策強化の流れが見られます。

カスハラ対策を考えているのであれば、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
弁護士に相談・依頼すれば、主に以下のようなサポートが受けられます。
|
ここでは、カスハラを弁護士に相談・依頼するメリットについて解説します。
カスハラ事案の発生直後の初期段階では、弁護士は事実関係の整理をおこないます。
顧客の要求内容や行為態様などを法的観点から分析し、カスハラに該当するかどうかを適切に判断してくれます。
この判断は、今後の対応方針を決定するうえで極めて重要な基礎となります。
法的リスクの評価なども弁護士の重要な役割のひとつです。
カスハラ事案は、企業側の対応次第では法的リスクが生じる可能性もあります。
弁護士は、安全配慮義務違反・不法行為責任・労働契約上の責任などの多角的な観点からリスクを評価し、適切な対応策をアドバイスしてくれます。
ほかにも、弁護士なら証拠保全の指導などもサポートしてくれます。
「どのような証拠をどのような方法で保全すべきか」「法的証拠能力を確保するためにはどのような手続きが必要か」など、法律知識に基づいて的確なアドバイスを提供してくれます。
対応方針の策定にあたっては「どこまでが企業の責任範囲で、どこからが顧客の不当な要求なのか」を明確に区分し、企業として取るべき対応や取るべきでない対応なども具体的に示してくれます。
カスハラ加害者との交渉代理や法的手続きの実施なども、弁護士の重要な役割のひとつです。
弁護士なら、カスハラ加害者との直接交渉・内容証明郵便の送付・調停や訴訟手続きの実施など、高度な知識や経験が求められる業務を代行してくれます。
カスハラ問題を根本的に解決するためには、事後対応だけでなく予防的なリスクマネジメント体制の構築が必要不可欠です。
弁護士なら、これまで培ってきた法律知識やノウハウを駆使して、包括的なリスクマネジメント体制の設計を支援してくれます。
過去の判例や他社事例なども参考にしながら、企業の業種・規模・顧客層の特性などを踏まえて、想定されるカスハラのリスクを体系的に分析してくれます。
労働関連法規・消費者保護法・個人情報保護法などのカスハラ対応に関連する法令なども把握しており、法改正への対応も含めて継続的なコンプライアンス体制の維持をサポートしてくれます。
弁護士による社内研修は、カスハラ対策を進めるうえで重要な役割を果たします。
十分な法律知識を有する弁護士が研修をおこなうことで、従業員の理解度の向上や実践的なスキルの習得などが図れます。
弁護士なら、実際の裁判例を題材として「どのような事案でどのような判断が下されたのか」「企業としてどのような点に注意すべきか」なども的確に解説してくれます。
成功事例と失敗事例の両方を紹介することで、適切な対応の重要性を理解することにつながるでしょう。

カスハラを弁護士に相談・依頼する際の選択肢としては、顧問弁護士・社内弁護士・法務受託・法務アウトソーシングなどがあります。
ここでは、それぞれの特徴やメリットについて解説します。
顧問弁護士は、社内に常勤・常駐するわけではないので、受動的な対応になる特質があります。
一方、完全に社外での独立した立場であることから「客観的なリスク分析・対応がなされる」というのも大きな特徴のひとつです。
月次の定例会議などを通じて潜在的なリスクについて継続的に検討できるほか、迅速な初期対応が望めるというのも顧問弁護士の強みです。
事案ごとに新たに弁護士を探したりする必要がないため、カスハラ事案が発生した際はすぐに相談・対応をおこなうことができます。
社内弁護士(インハウスローヤー)の場合、企業内部にいるからこそ密接で継続的な支援が受けられるというのが大きな特徴のひとつです。
社内弁護士は企業内部にいるため、カスハラ事案が発生した際には即座に対応でき、経営陣や関係部署と連携してリアルタイムで意思決定をおこなうことができます。
また、企業の事業戦略や経営方針を現場で深く理解している社内弁護士は、単なる法的対応にとどまらず、ビジネス上の影響も考慮した総合的な解決策を提案できます。
企業の組織文化・価値観・従業員の特性なども把握しているため、企業の実情に即したカスハラ対策を設計できます。
顧問弁護士と社内弁護士の中間的な関与形態として、法務受託・法務アウトソーシングという選択肢もあります。
特に、社内に法務部門や社内弁護士を持たない中小企業にとって有効な選択肢となります。
主に外部の法律事務所がチームを組んで法務機能を受託し、カスハラ問題を得意とするチームが対応することで、単独の弁護士では対応が困難な大規模案件や複雑な事案にも適切に対処できます。
法務受託サービスでは、過去の豊富な経験に基づいて標準化された対応プロセスが構築されているため、一定の品質が保証されたサービスを受けることができます。
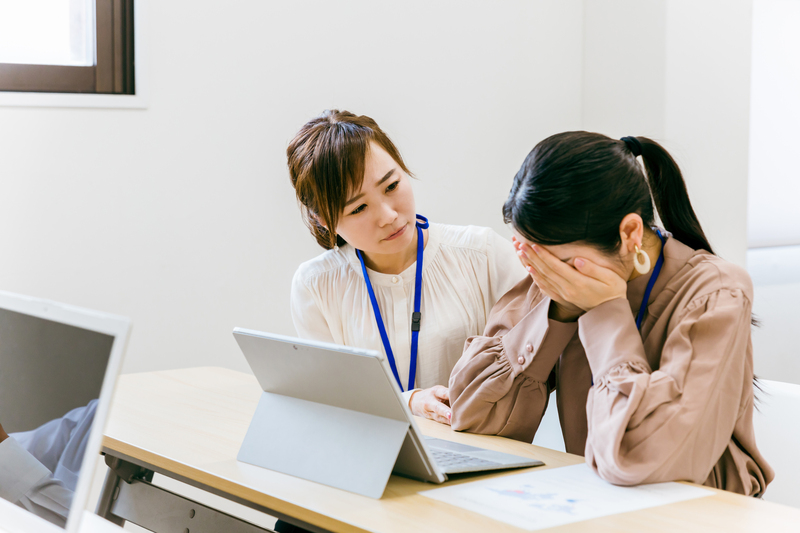
カスハラに伴い、企業にとってはどのようなリスクがあるでしょうか。
ここでは、労務面・人事面・レピュテーションなどの観点から解説します。
カスハラが企業にもたらす労務面のリスクは多岐にわたります。
特に大きなリスクの一つが「安全配慮義務違反による損害賠償責任」です。
企業は労働契約に基づき、従業員が安全で健康的な環境で働けるように配慮する義務を負っています。
たとえば、カスハラが原因で従業員が精神疾患を発症した場合に「企業が適切な対策を講じていなかった」と判断されれば、治療費・休業損害・慰謝料などの損害賠償を請求される可能性があります。
また、カスハラによる精神疾患について「業務起因性あり」と認定されれば、企業は労災保険料率の上昇やメリット制の悪化といった経済的負担を負うことになります。
ほかにも、労災認定された事案では労働基準監督署による調査対象となり、職場環境の改善命令が出されたりする可能性もあります。
カスハラによる人事面の主なリスクとしては、従業員の離職率上昇・従業員のモチベーション低下・従業員の休職者増加などがあります。
カスハラによる直接的な影響としては、従業員の離職率上昇があります。
カスハラを受けた従業員は、精神的ストレスから職場に対して不信感を抱き、転職を選択するおそれがあります。
優秀な人材の流出は企業にとって大きな損失であり、経験豊富な従業員が離職することで業務の継続性が損なわれ、新人研修や引き継ぎコストなどが発生します。
また、カスハラ問題で話題となった企業は求職者からの評価も下がり、新たな人材の確保が困難になる可能性もあります。
従業員のモチベーション低下も深刻な問題のひとつです。
カスハラを受けた従業員だけでなく、同僚や部下も職場環境に対して不安を感じ、業務に対する意欲が減退するおそれがあります。
結果的に、サービス品質の低下・生産性の減少・チームワークの悪化といった問題が連鎖的に発生することもあります。
メンタルヘルス不調による休職者の増加も、人事面の大きなリスクです。
カスハラによってうつ病や適応障害などを発症した従業員が長期休職に入れば、人員不足が発生して残された従業員の負担が大きくなります。
従業員の負担が大きくなることで、さらなるメンタルヘルス不調者が発生するという悪循環に陥る可能性もあります。
カスハラによる主なレピュテーションリスクとしては、SNSでの炎上・マスメディアによる報道・.顧客離れなどがあります。
SNSでの炎上は特に深刻です。
なかには、カスハラ加害者が自らの行為を正当化するために、企業側の対応を一方的に批判するような投稿をおこなうケースもあります。
企業に対するネガティブな投稿が拡散されることで、事実と異なる情報が一人歩きし、企業の評判が大きく損なわれる可能性があります。
一度炎上した情報はインターネット上に長期間残り、企業ブランドに長期的な悪影響を与え続けます。
マスメディアによる報道などのリスクもあります。
カスハラ問題が社会的関心を集める中、企業による不適切な対応は報道機関の注目を集めやすくなっています。
従業員への配慮を欠いた対応やカスハラ加害者への過度な迎合などをしてしまうと、ブラック企業としてレッテルを貼られてしまうおそれもあります。
顧客離れのリスクも無視できません。
カスハラ問題への対応を通じて企業の価値観や従業員に対する姿勢なども見えてくるため、適切な対応をおこなわない企業に対して良識ある顧客が離れていく可能性があります。
特に、若い世代の消費者は企業の社会的責任を重視しやすく、従業員を守らない企業の商品・サービスなどを敬遠する傾向があります。
上場企業の場合、カスハラ問題による企業イメージの悪化は株価の下落要因となるおそれもあります。
投資家は企業の持続可能性を重視するため、従業員の離職率上昇や生産性低下につながるカスハラ問題は、投資判断に負の影響を与えることが予想されます。

カスハラ事案が発生した際、企業としては問題顧客との対応・対応した社員へのケア・社内での対応フローの整備などを速やかに進める必要があります。
ここでは、カスハラ問題における企業側の対応について解説します。
カスハラ事案では、問題顧客に対して以下のような対応を取ることが大切です。
問題顧客に対しては、段階的なアプローチが必要となります。
初期段階では、冷静さを保ちながら顧客側の話を聴きましょう。
無制限に顧客側の要求を聞き入れるというわけではなく、あくまでも事実関係を正確に把握し、要求内容の妥当性を冷静に判断することが主な目的です。
初期段階で重要なのは、感情的にならず、記録を残すことです。
次に、要求内容の分析と線引きをおこないます。
顧客の要求が正当なものか、社会通念上不相当なものかを客観的に判断する必要があります。
正当な要求に対しては誠実に対応し、不当な要求に対してはきっぱりと断る姿勢が必要です。
判断基準を明確にして全社で共有しておくことで、一貫した対応が可能となります。
対応の記録化・証拠保全なども欠かせません。
カスハラ事案では、後日事実関係が争われることも多くあるため、会話の内容・日時・担当者・顧客側の態度や発言などを詳細に記録しておく必要があります。
できれば録音も検討すべきですが、事前に相手方の同意を得るか、法的な要件を満たす形で実施する必要があります。
組織的な対応として、エスカレーション体制の構築も重要です。
カスハラ事案で大切なのは、窓口として対応した現場の担当者を1人にしないことです。
対応が困難な場合は速やかに上司や専門部署に報告し、組織的な対応に移行する仕組みが必要です。
エスカレーションの基準を明確にし、担当者が躊躇なく報告できるように環境を整備しましょう。
カスハラ事案において、実際に対応にあたった社員へのケアも極めて重要です。
適切なケアを怠ってしまうと、従業員の精神的健康に深刻な影響を与え、企業の安全配慮義務違反にもつながる可能性があります。
対応した社員に対しては、以下のような対応を取りましょう。
まずは、即時のメンタルヘルスケアをおこないましょう。
カスハラに対応した従業員は強いストレスや不安を感じているため、事案発生後は速やかに従業員の心理状態を確認し、必要に応じて専門的なカウンセリングを提供する必要があります。
産業医や外部のEAP(従業員支援プログラム)サービスとの連携体制を事前に構築しておくことが大切です。
上司や同僚からのサポートも必要不可欠です。
カスハラを受けた従業員が孤立感を感じないよう、チーム全体でサポートする環境を作っておく必要があります。
くれぐれも「お客様だから仕方ない」「もっと我慢すべき」といったような対応は避けましょう。
従業員の人権を尊重して「カスハラは決して許されない行為である」ということを明確に示すことが大切です。
また、カスハラを受けた従業員は精神的負担から通常の業務にも支障をきたすおそれもあるため、一時的に業務量を調整したり、顧客対応から外したりするなどの対応も検討しましょう。
カスハラ問題に組織的に取り組むためには、明確な対応フローの整備が必要不可欠です。
社内においては、以下のような対応を取りましょう。
まずは、カスハラの定義と判断基準を明確にする必要があります。
「どのような行為がカスハラに該当するのか」「どの程度の要求が不当とみなされるのか」などについて、具体例を交えながら基準を設定します。
現場の担当者が迷わずに判断できるよう、できる限り具体的でわかりやすいものにしておくことが大切です。
報告体制の構築も重要です。
具体的には、カスハラ事案が発生した場合の報告先・報告方法・報告期限などを明確に定めておきましょう。
報告を受ける部署や担当者を指定し、24時間体制での対応が必要な場合は緊急連絡体制も整備しておきます。
また、報告者が不利益を受けないよう、守秘義務や報復防止の仕組みなどもあわせて整備しておくことも大切です。
対応レベルの分類と対応方針の策定も必要です。
カスハラの程度や内容に応じて対応レベルを分類し、それぞれのレベルに応じた対応方針を事前に定めておきましょう。
軽微なケースから深刻なケースまで段階的な対応ができるよう、詳細なマニュアルを作成しておくことが大切です。
関係部署との連携体制の構築も欠かせません。
人事部・法務部・広報部・セキュリティ部門など、カスハラ事案に関わる可能性がある全ての部署との連携体制を構築しておく必要があります。
それぞれの役割と責任を明確にし、スムーズな情報共有と対応ができる仕組みを作っておきましょう。

ここでは、カスハラ問題に対する主な予防策・対応策について解説します。
カスハラ問題に対する予防策としては、ケーススタディの実施・対応フローやマニュアルの整備・定期的な研修の実施・ロールプレイなどがあります。
カスハラに関しては、従業員の心理的安全確保の観点から予防策を立てておくことも大切です。
たとえば、CS(カスタマーサポート)などの顧客対応部門でのケーススタディの実施は、効果的な予防策のひとつです。
実際に発生したカスハラ事案や他社の事例などを基に、ケーススタディを定期的に実施することで、現場担当者の判断力や対応スキルの向上を図ることができます。
ケーススタディでは、事案の背景・顧客の心理状態・対応の選択肢・それぞれの対応がもたらす結果などを多角的に分析します。
参加者がロールプレイを通じて体験することで、理論だけでは得られない実践的なスキルを身につけることができます。
カスハラ事案発生時の対応フローやマニュアルの整備は、組織的な予防策として必要不可欠です。
明確で実用的なマニュアルがあることにより、現場担当者は迷わずに適切な対応を取ることができ、カスハラによる被害拡大の防止につながります。
マニュアルには、カスハラの定義・判断基準・対応の基本原則・段階別の対応方法・エスカレーション基準・記録の取り方・関係部署への連絡方法などを具体的に記載することが大切です。
また、よくある質問と回答集(FAQ)としてケースレベルに落とし込んだものを構築し、現場担当者が即座に参照できるようにしておくなどの工夫も効果的です。
社内での定期的な研修の実施やロールプレイなどは、従業員のスキル向上や意識啓発の両面で重要な役割を果たします。
基本的には年1回以上の定期研修を実施し、カスハラに関する基礎知識・対応技術・法的知識などを体系的に学習する機会を提供しましょう。
研修では、講義形式だけでなくグループディスカッションやロールプレイを積極的に取り入れることで、参加者の相互的な理解度の向上や実践的なスキル習得が図れます。
特にロールプレイでは、さまざまなパターンのカスハラ事案を想定し、参加者が実際の対応を体験することで、現実的な対応能力を身につけることができます。
実際にカスハラが発生した際は、マニュアルに沿った対応や証拠保全などを速やかにおこないましょう。
実際にカスハラが起きた際は、従業員が顧客と対峙して疲弊しないよう、形式的に対応できるようにしておくことが大切です。
事前に整備されたマニュアルに従って一貫した対応をおこなうことで、対応品質の標準化や担当者の負担軽減を実現できます。
マニュアルには、初期対応から問題解決まで、各段階での具体的な行動指針を明記します。
もしマニュアルだけでは解決が困難な特殊なケースについては、速やかにエスカレーションするよう判断基準なども明確に定めておく必要があります。
現場担当者が一人で抱え込まず、組織的な対応に切り替えるタイミングを明確にしておくことで、問題の深刻化を防止できます。
また、企業として対応すべき範囲なども明確に定義しておき、範囲を超えるような要求に対しては毅然とした態度で断ることも必要です。
顧客とのやり取りの録音などの証拠保全は、後日の紛争に備えて必要不可欠な対応策のひとつです。
カスハラ事案では事実関係が争点となることが多いため、客観的な証拠の保全が重要になります。
録音時は原則として相手方の同意を得ることが望ましいですが、業務上の必要性がある場合や従業員の安全確保のために必要な場合は、事前に録音する旨を告知したうえで実施することも可能です。
録音以外にも、メールやSNSでのやり取りの保存・防犯カメラの映像の保全など、さまざまな形での証拠保全を検討しましょう。

カスハラは、現代の企業が直面する重要な経営課題のひとつとなっています。
単なる顧客対応の問題ではなく、従業員の人権保護・企業の法的責任・社会的信用に関わる包括的な問題として捉える必要があります。
カスハラに対しては、予防策の構築から実際の事案対応まで体系的かつ専門的なアプローチが必要不可欠です。
法律知識を有する弁護士のサポートは、問題の早期解決や企業リスクの最小化において非常に効果的です。
当サイト「企業法務弁護士ナビ」では、カスハラなどの対応が得意な全国の弁護士を掲載しています。
相談内容・業界・地域から対応可能な弁護士を一括検索でき、法律相談だけの利用も可能ですので、カスハラ対策を考えているのであれば気軽にご利用ください。

