弁護士とマッチングできます
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。


企業にとって情報管理の重要性は、いくら強調してもし過ぎることはありません。企業が取り扱う情報は、自社のノウハウ・顧客の個人情報・取引に関する情報など、そのほとんどが機密情報に該当すると言っても過言ではないでしょう。
しかし企業が他の企業と取引を行う際には、交渉・検討を行う上での前提となる材料として、一定の機密情報を相手方に開示する必要があります。
その際に締結されるのが「機密保持契約書」(NDA)です。
機密保持契約書は、機密情報の予期せぬ流出を防ぐための契約書です。
しかし、具体的にどのような内容を盛り込めば良いかということについては、あまりよく知らないという方も多いかと思います。そこでこの記事では、機密保持契約書に規定すべき内容について、すぐに利用していただけるひな形ともに詳しく解説します。

まず、そもそも機密保持契約書とはどのような契約書なのかについて解説します。
機密保持契約書は、当事者間で相互に(又は一方から)開示される情報について、無断で第三者に開示・漏洩されることを防ぐことを約束する内容の契約書です。
会社同士が取引関係に入る場合、その後に取引に関して機密情報のやり取りが行われることが想定されます。そのため、取引についての本格的な交渉に入る前の段階で、機密保持契約書が締結されることになります。
機密性の高い情報の無断開示・漏洩を防ぐことを目的とする契約書には、「機密保持契約書」の他にも、「秘密保持契約書」「守秘義務契約書」などのさまざまな別名があります。
しかし、これらの契約内容・目的・機能は基本的に同じと理解して良いでしょう。
機密保持契約書のひな形を紹介します。適宜自社のビジネスに沿った形にアレンジしてご利用ください。
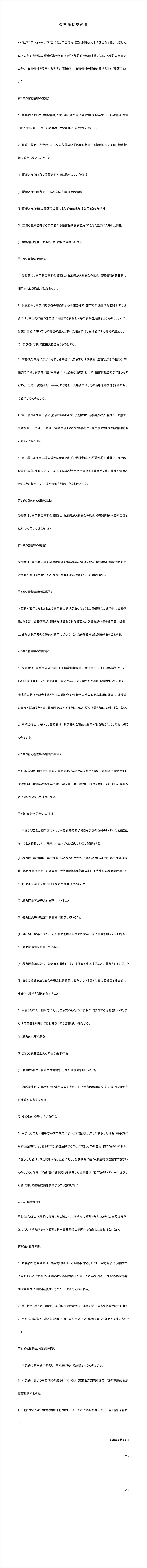
前章で紹介した機密保持契約書のひな形に沿って、各条項が持つ意味や機能を解説します。
機密保持契約書の冒頭では、機密保持義務の対象となる「機密情報」が定義されます。
一般的には、口頭・書面などの形式を問わず、当事者間でやり取りされるすべての情報が機密情報とされることが多いです。ただし、公知情報などの機密性がない情報に関しては、「機密情報」の定義から除外されます。
機密保持契約書の中心的な内容として、相手方の承諾なく、開示を受けた機密情報を第三者に開示してはならないという機密保持義務が規定されます。
ただし、公的機関から要請されてどうしても機密情報を開示しなければならない場合もあります。また、取引を行う上で、役員および従業員、専門家との間で機密情報に関するやり取りが行われるケースもあります。
こうした場合は、逐一相手方の承諾を取らなければならないとするのは煩雑なので、機密保持義務の例外として明記されるのが通常です。
機密保持契約書は取引の前段階で締結されるものなので、機密情報は取引に関係する目的に限定して利用されることが想定されています。そのため、取引に関係がない目的で機密情報を利用してはならない旨が規定されます。
機密情報の漏洩などが発生する危険性を最小化するため、開示者の承諾なく、機密情報の複製・複写・改変を行ってはならない旨が規定されます。
ただし実際には、社内での情報共有などの目的で資料のコピーを行いたい場合もあるかもしれません。そのため、契約交渉の内容次第で、取引の目的に利用するための最小限のコピーなどについての例外を設ける場合もあります。
機密情報を開示した側としては、情報漏洩を防ぐため、開示後もできる限り機密情報の流通経路をコントロールしたいところです。そのため、機密保持契約が終了した場合などについては、受領者が機密情報を返還または破棄する義務が定められます。
機密情報が万が一漏洩してしまった場合には、速やかに漏洩した機密情報の回収や再発防止などの対応を取る必要があります。
また開示者側としても、機密情報漏洩の被害を受ける可能性があります。そのため、受領者側から漏洩状況などの報告を受け、必要に応じて受領者に対して指示を出せるようにしておくことも必要です。
このような漏洩時の対応についても、機密保持契約書の中で規定されることが多いです。
契約一般に見られる規定として、契約上の地位および権利義務を相手方に無断で譲渡してはならないことが定められます。当事者双方の合意による契約である以上は当然のことですが、注意的に規定されることが多いです。
反社条項もさまざまな契約において規定されており、機密保持契約書においても同様に規定されることがあります。最近では暴力団排除の流れが強まっているので、反社条項も詳細に規定されることが多くなっています。
実際上は当事者が反社会的勢力に該当することが想定されないとしても、会社のポリシーやコンプライアンスとの関係で入れておくことが通常です。具体的な内容については、自社の暴力団排除に関するポリシーも確認しつつ、相手方と調整することになります。
損害賠償規定については、「故意または過失がある場合に相当因果関係の範囲内で損害を賠償する」という民法の原則を確認するのが通常です。
しかし、契約交渉の内容によっては、民法の基準よりも責任範囲を拡大または限定することもあります。たとえば、損害賠償の対象を「一切の損害」に拡大したり、損害賠償責任を負担する条件を「故意または重過失がある場合」に限定したりするなどのパターンが考えられます。
機密保持契約書は、取引を検討する前提として締結されるものなので、有効期間も取引期間をカバーするように合理的な期間が設定されます。
なお、機密保持の実効性を確保する観点から、契約終了後も機密保持義務が存続するとされている場合も多いところです。ただし、永続的な機密保持義務を負うことは、当事者にとって機密情報として管理する負担が重いため、契約終了後一定期間に限定されるケースもよく見られます。
企業法務の契約書には一般的に見られる規定として、準拠法および管轄裁判所についての合意が定められます。特に海外の法人などと機密保持契約を締結する際には、日本法が準拠法であることを明確化しておきましょう。
なお、管轄裁判所の合意については、第一審においてのみ適用されます。
機密保持契約書を作成する際には、弁護士に依頼をしてチェックを受けることをおすすめします。
機密保持契約書の本来の目的からして、最低限情報漏洩を十分に防げる内容になっているかのチェックが必要となります。また、機密情報の範囲・開示できる場合の例外・機密保持義務の存続期間・損害賠償の範囲など、相手方との契約交渉の余地が意外とあることも事実です。
弁護士は、機密保持契約書の締結に関するポイントに精通していますので、契約書が依頼者にとって十分な内容になっているかのチェックを抜かりなく行います。
さらに相手方から契約条件についての要求や提案が行われた際にも、
ということについて法的なアドバイスを受けられます。
機密保持契約書についての契約交渉を行う際には、ぜひ弁護士にご相談ください。
機密保持契約書の締結は、企業にとって情報管理の観点から非常に重要です。
弁護士に依頼をしてしっかりとした機密保持契約書を作成すれば、その後の取引を安心して推し進めることができます。既に自社で使用しているひな形があるという場合も、一度弁護士のチェックを受けてみてはいかがでしょうか。

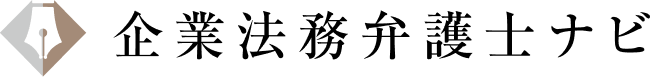 編集部
編集部
本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。
※企業法務弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
