弁護士とマッチングできます
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。

経営者として「会社をたたむ」という決断は、人生において最も重い選択の一つです。
業績不振、後継者不在、事業環境の変化など、その理由は様々ですが、多くの経営者が「どのような手続きを取れば良いのか」「従業員や取引先にどう対応すべきか」といった不安を抱えています。
会社をたたむ方法は一つではありません。
通常の解散・清算から、特別清算、破産手続き、さらには廃業以外の選択肢として事業承継やM&Aまで、様々な選択肢が存在します。
それぞれにメリット・デメリットがあり、会社の財務状況や事業の将来性によって最適な方法は異なります。
本記事では、会社をたたむ際の具体的な手続き、必要な費用、期間、そして経営者が知っておくべき実務上のポイントまで、弁護士の視点から詳しく解説いたします。
一人で悩まず、まずは全体像を把握することから始めましょう。

「会社をたたむ」という表現は法律用語ではありませんが、一般的には会社の事業活動を終了させ、法人格を消滅させることを指します。
法的には、解散、清算、破産、民事再生(会社更生)の大きく4つが考えられます。
解散・清算とは、会社が営業活動を停止し、清算手続きに入ることを意味します。
会社法第471条に基づき、株主総会の特別決議などにより解散が決定されます。
解散しただけでは会社の法人格は消滅せず、清算手続きを経て初めて会社が完全に消滅します。
清算手続は、会社の財産を処分し、債権者に弁済を行い、残余財産があれば株主に分配する手続きです。
会社法第475条以降に詳細な規定があります。
清算には、裁判所の関与がない「任意清算(通常清算)」と、裁判所の監督下で行われる「特別清算」があります。
破産は、会社が債務超過に陥り支払い不能となった場合に、裁判所の監督下で会社財産を換価し、債権者に公平に配当する手続きです。
破産法に基づく法的整理の一種です。
民事再生は、経済的に窮境にある会社が事業を継続しながら再建を図る手続きですが、再建が困難な場合には清算型の民事再生として会社をたたむ選択肢にもなります。
会社更生もこれに類する手続ですが、詳細は後述します。
これらの手続きは、会社の財務状況、債権者との関係、事業の継続可能性などによって使い分けられます。

まず、会社がどのようなきっかけで事業を縮小、たたんでいくきっかけになるのか、そのケースとして3つ解説していきます。
中小企業白書(2023年版)によれば、中小企業経営者の高齢化が進んでいます。
2000年に経営者年齢のピークが「50~54歳」となり、2020年と2022年は「60~69歳」「70~74歳」が高割合となる傾向となっています。
参照:中小企業白書|第1節 事業承継・M&A 〔2〕経営者の高齢化
さらに、そのうち約半数が後継者未定という深刻な状況です。
後継者不在による廃業は、業績が黒字であっても発生します。
経営者が高齢となり、かつ親族や従業員の中に事業を引き継げる人材がいない場合、やむを得ず廃業を選択するケースが増加しています。
経済産業省の「事業承継ガイドライン」(2022年改訂版)では、早期からの後継者育成や第三者承継(M&A)の検討を推奨しています。
後継者不足を理由に廃業を考える前に、事業承継支援機関への相談や、後述するM&Aの活用を検討することが重要です。
スタートアップや成長企業において、事業モデルの転換(ピボット)のために既存の会社を整理するケースがあります。
新規事業への集中のため、採算の取れない事業を切り離したり、会社自体を清算して新会社で再スタートしたりする戦略的な選択です。
特にベンチャー企業では、市場環境の変化に応じて迅速な方向転換が必要となります。
その際、既存の会社組織が足かせとなる場合、計画的に会社をたたんで新たな事業に資源を集中させることは、経営判断として合理的です。
ただし、ピボットを理由に会社をたたむ場合でも、債権者や従業員への適切な対応は不可欠です。
特に従業員の雇用については、新会社での再雇用や転職支援など、誠実な対応が求められます。
最も深刻なのが、債務超過や資金繰りの行き詰まりにより、会社をたたまざるを得ないケースです。
帝国データバンクの「全国企業倒産集計」(2024年)によれば、2024年度の倒産件数は1万70件(前年度8881件、13.4%増)となり、3年連続で前年度を上回る結果となっています。
特に、『サービス業』(前年度2187件→2638件、20.6%増)が最も多く、『小売業』(同1874件→2109件、12.5%増)、『建設業』(同1749件→1932件、10.5%増)となっています。
出典:帝国データバンク|倒産集計 2024年度報(2024年4月~2025年3月)
債務超過とは、会社の負債総額が資産総額を上回る状態を指します。
この状態が続き、支払い不能に陥ると、法的には破産原因が存在することになります(破産法第15条)。
債務整理の必要性が生じた場合、経営者は早期に専門家に相談し、適切な手続きを選択することが重要です。
放置すると、債権者からの訴訟や差押えなどの強制執行を受け、事態がさらに悪化する可能性があります。
また、財務状況が悪化してからの対応では、選択できる手続きが限られてしまいます。

会社をたたむことを検討する前に、事業や会社を存続させる方法がないか、まず検討すべきです。
特に技術力や顧客基盤など価値ある経営資源を持つ会社の場合、廃業は社会的損失にもなりかねません。
吸収合併とは、一つの会社が他の会社を吸収し、吸収された会社は消滅する組織再編手続きです(会社法第748条)。
後継者不足の会社が同業他社に吸収合併されるケースが典型的です。
吸収合併のメリットは、事業の継続性が保たれ、従業員の雇用も維持されやすい点です。
また、合併による相乗効果(シナジー)が期待できる場合もあります。
債務については、存続会社が包括的に承継するため、債権者保護手続きが必要です(会社法第789条)。
中小企業基盤整備機構の「M&A支援」などを活用すれば、適切な合併相手を見つけることも可能です。
会社分割は、会社の事業の全部または一部を他の会社に承継させる組織再編手続きです(会社法第757条以降)。
不採算事業を切り離し、収益性の高い事業のみを他社に承継させることができます。
新設分割と吸収分割の2種類があり、新設分割は新たに会社を設立してそこに事業を承継させる方法、吸収分割は既存の会社に事業を承継させる方法です。
会社分割を利用すれば、事業の一部は存続させつつ、残った会社は清算するという選択も可能です。
ただし、債権者保護手続きや労働契約の承継に関する手続き(労働契約承継法)が必要となります。
事業譲渡とは、会社の事業の全部または一部を他の会社に売却する取引です(会社法第467条)。
組織再編とは異なり、個別の資産・負債・契約の移転が必要となります。
事業譲渡のメリットは、譲渡する資産・負債を選択できる点です。
不要な負債を残したまま、価値ある事業のみを売却できます。
譲渡代金を債務の弁済に充てることで、円滑な清算が可能となる場合もあります。
中小企業庁の「事業承継・引継ぎ補助金」を活用すれば、M&A仲介費用の一部補助を受けられる場合もあります。
株式譲渡は、会社の株主が保有する株式を第三者に譲渡することで、会社の支配権を移転する方法です。
中小企業のオーナー経営者の事業承継で最も多く利用されます。
株式譲渡のメリットは、手続きが比較的簡便で、会社の事業や組織、契約関係がそのまま維持される点です。
従業員の雇用も継続され、取引先との関係も変わりません。
ただし、株式譲渡の場合、会社の負債も含めて全てが承継されるため、買い手が見つかりにくい場合もあります。
デューデリジェンス(企業調査)で問題が発見されると、譲渡価格の減額や取引の中止につながる可能性もあります。
休眠会社化とは、事業活動を停止しながらも会社の法人格は維持する選択肢です。
将来的な事業再開の可能性がある場合や、許認可を保持したい場合などに活用されます。
休眠会社であっても、法人住民税の均等割(年間7万円程度)や登記維持のための費用は発生し続けます。
また、12年間登記を放置すると、みなし解散の対象となります(会社法第472条)。
休眠会社化は暫定的な措置であり、長期的には事業再開か清算かの判断が必要です。
ただし、経営環境の変化を見極める時間的余裕が得られるメリットはあります。
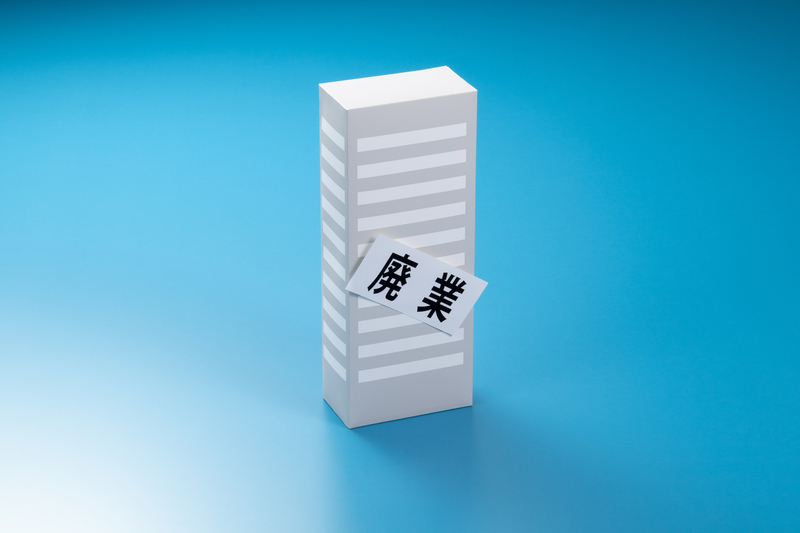
実際に会社をたたむ際の方法・選択肢について解説していきます。
解散・任意清算、特別清算、法的倒産手続の3つのカテゴリーでみていきます。
任意清算(通常清算)は、債務超過でない会社が自主的に事業を終了させる最も一般的な方法です。
会社法第475条以降に規定されていますが、以下の適用条件があります。
適用条件
会社が債務超過でないこと(資産が負債を上回る状態)
株主総会の特別決議により解散が決議されること
債権者全員に弁済できる見込みがあること
手続きの特徴 裁判所の関与がないため、手続きが比較的簡便で費用も抑えられます。
清算人(通常は代表取締役が就任)が中心となって財産の処分、債務の弁済、残余財産の分配を行います。
メリットは、期間と費用の軽量さで、費用はおよそ20万円程度からで、1年程度のスパンで進めることができる点です。
デメリットは、債務超過の場合は利用できず、特別清算や破産に移行せざるを得ない点です。
特別清算は、債務超過の疑いがある場合(実際には債務超過でないがそれに近いような状態)や、清算の遂行に著しい支障がある場合に、裁判所の監督下で行われる清算手続きです(会社法第510条以降)。
次のような条件があります。
適用条件
株式会社が解散していること
債務超過の疑いがあること、または清算の遂行に著しい支障があること
債権者の同意が得られる見込みがあること
手続きの特徴
裁判所が選任する清算人や監督委員の監督下で手続きが進行します。
進行においては、債権者集会での協定案の可決(出席債権者の過半数かつ債権額の3分の2以上の同意)が必要です。
任意清算よりも費用は高くなるものの、柔軟な債務整理が可能な点はメリットです。
デメリットは、債権者の協力が得られない場合は成立せず、破産に移行せざるを得ない点です。
法的な倒産手続きについて、破産、民事再生そして会社更生の3つに分けて解説していきます。
○破産
破産は、債務超過で支払い不能となった会社が、裁判所の監督下で全財産を換価し、債権者に公平に配当する手続きです(破産法第15条以降)。
支払い不能または債務超過であること(破産法第15条、第16条)が必要であり、破産手続開始申立てをすることになります。
全く資産0の状態であれば、理論上はいわゆる同時廃止も考えられますが、現実的には管財事件として裁判所が選任する破産管財人が会社の財産を管理・換価し、債権者に配当します。
経営者は会社の経営権を完全に失います。
会社は法人格が消滅し、完全に消滅します。
メリットは、債務整理が確実に完了し、経営者が法的責任から解放される点です(ただし個人保証債務は別で、経営者個人の債権債務関係として整理されます。)。
デメリットは、債権者や債務総額によって費用が高額になりうることがデメリットです。
東京地方裁判所の「破産事件の運用」によれば、2023年の法人破産申立件数は約5,000件で、そのうち約8割が中小企業でした。
○民事再生
民事再生は、経済的に窮境にある会社が事業を継続しながら再建を図る手続きですが、再建が困難な場合は清算型の民事再生もあり、シームレスな運用とされるのが実務上一般的です。
破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあることとともに、事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できないことが条件となります。
原則として経営者が引き続き会社を管理する(DIP(debt in possetion)型)ため、事業継続が可能です。
再生計画案を作成し、債権者の同意(議決権者の過半数かつ議決権額の2分の1以上)を得て認可を受けることにより、再生手続がスタートします。
事業の継続が困難な場合、民事再生手続きの中で会社の財産を処分し、債権者に弁済する「清算型」も活用されます。
この場合、破産よりも柔軟な処理が可能となる場合があります。
メリットは、事業を継続しながら債務整理ができる点、経営権を維持できる点です。
デメリットは、手続きが複雑で費用が高額(予納金200万円~)になる点で、中小企業では利用が困難な場合が多い点です。
ただ、法人格も消滅せず事業継続を通じた債権者の保護・債務者の再生を目的としているため、厳密には会社をたたむというものとは少し毛色が異なります。
〇会社更生
会社更生は、株式会社が経済的に窮境にある場合に、事業の維持更生を図ることを目的とした再建型の法的整理手続きです(会社更生法第1条以降)。
破産や民事再生と異なり、大企業の再建において主に利用されています。
株式会社であることが前提で、破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあることと事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済できないことが要件とされます(会社更生法第17条)。
会社更生手続きは、次のような点で他の倒産手続きと大きく異なります。
管財人による経営: 裁判所が選任する更生管財人が会社の経営権を掌握し、現経営陣は原則として経営から退きます(会社更生法第72条)
株主の権利: 株主の権利は更生計画で定めるところに従い、減資や株式の無償消却が行われることが一般的です
担保権者の扱い: 担保権の実行が禁止され、担保権者も更生計画に従う必要があります(会社更生法第47条)。
この点が民事再生と大きく異なります
包括的な再建: 株主、債権者、従業員など全てのステークホルダーを巻き込んだ抜本的な再建が可能です
会社更生は、実務上主に以下のような大企業で利用されます。
上場企業や大規模な株式会社
多数の債権者や株主を抱える企業
社会的影響が大きく、事業継続の必要性が高い企業
担保権者の権利を制限してでも再建を図る必要がある企業
中小企業庁の「中小企業実態基本調査」によれば、会社更生手続きの利用は年間数件程度と極めて限定的です。
これは手続きが複雑で費用が高額であり、中小企業には適さないためです。
東京地方裁判所の運用では、負債総額100億円未満の場合で予納金500万円程度が目安とされています。
出典: 裁判所「会社更生事件の手続」

会社をたたむ場合、どの程度の費用と期間を要するでしょうか。
費用の内訳としては、次のようなイメージです。
l 登記費用:解散登記3万円
l 清算結了登記2,000円
l 官報公告費:約3万円~4万円(債権者への公告)
l 専門家報酬:弁護士・司法書士費用10万円~30万円程度
l その他:会計監査費用、税務申告費用など
合計で約20万円~50万円が想定されます。
ただし、会社の規模や資産の処分状況により変動します。
所要期間として、解散決議から清算結了まで:3か月~1年程度、債権者への公告期間が最低2ヶ月必要(会社法第499条)となります。
そして、財産の処分や税務処理に時間を要する場合はさらに長期化する場合もあります。
なお、株式会社の場合、清算事務年度ごとに決算報告を作成し、株主総会の承認を得る必要があります(会社法第507条)。
費用の内訳は、次のようなイメージになります。
l 予納金:50万円~100万円程度(裁判所により異なる)
l 官報公告費:約5万円~10万円
l 弁護士費用:50万円~150万円程度
l 監督委員報酬:月額10万円~30万円程度
合計で約100万円~300万円が一般的です。
債権額や会社の規模により変動します。
所要期間としては、特別清算開始決定から終結まで:6か月~2年程度とされます。
債権者集会での協定案可決が必要で、その後協定案の認可決定後、弁済計画に従って弁済する形で進行します。
東京地方裁判所の運用では、債権者数が少なく協定が円滑に成立する場合、1年以内に終結するケースが多いとされています。
費用の内訳としては、次のようなイメージになります。
予納金:最低50万円~(負債総額により変動、1億円超では200万円以上も)
官報公告費:約2万円~3万円
弁護士費用:50万円~200万円程度(事案の複雑さによる)
その他:破産管財人の報酬は予納金から支払われる
なお、東京地方裁判所の「予納金基準」によれば、負債総額5,000万円未満の場合、予納金は70万円程度です。
合計で最低100万円~、規模の大きい会社では数百万円以上必要となります。
所要期間は、破産手続開始決定から終結まで1年~2年程度、換価対象資産が多いあるいはプロセスが多いなど財産の換価に時間を要する場合はさらに長期化することも想定されますし、債権者が多数の場合や財産関係が複雑な場合も長期化します。
また、破産法第75条により、破産管財人は遅滞なく換価を行う義務がありますが、不動産売却などで時間を要するケースが多くあります。
なお、費用が準備できない場合 破産費用が準備できない場合、以下のような方法があります。
法テラスの民事法律扶助制度の利用(資力要件あり)
弁護士への分割払い相談
少額管財手続き(東京地裁などで運用、予納金20万円~)
ただし、予納金の準備ができない場合、破産申立て自体が困難となるため、早期の資金確保が重要です。

会社をたたむ際に行われる手続の流れについて、方式ごとに解説していきます。
解散及び清算の流れは、次のとおりです。
清算は、ここでは任意清算に絞って解説します。
株主総会で解散の特別決議を実施します。(会社法第309条2項11号)
議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。
同時に清算人を選任します。(通常は代表取締役が就任)
解散決議から2週間以内に、本店所在地の法務局で解散登記及び清算人選任登記を行います。
登記完了後、会社は清算会社となります。
官報に債権者に対する公告を掲載し、知れている債権者には個別に催告します。(会社法第499条)
債権申出期間は最低2ヶ月必要です。
会社の財産を処分して金銭に換え、債権者に弁済します。
売掛金の回収、在庫の処分、不動産の売却などを実施
全ての債務を弁済した後、残余財産があれば株主に分配します。(会社法第502条)
持株比率に応じて分配します。
清算人は決算報告書を作成し、株主総会で承認を得ます。(会社法第507条)
株主総会の承認から2週間以内に清算結了登記を実施します。
登記完了により、会社の法人格が消滅します。
破産手続きの大まかな流れは、次のとおりです。
破産手続きを検討する段階で、弁護士など専門家に相談し、財務状況の分析、従業員・取引先への対応方針を検討します。
他の手段とも比較します。
破産を選択する場合、必要書類を準備します。
(例:破産申立書、債権者一覧表、財産目録など)
同時に、従業員への解雇予告、取引先への通知準備なども行います。
裁判所に破産手続開始の申立てを実施します。
予納金の納付も行います。
申立てから1週間~1ヶ月程度で、裁判所が破産手続開始の要件を審査し、決定します。
同時に破産管財人が選任されます。
債権者の把握と、債権額の確定を行います。
破産管財人が会社の財産を調査・管理し、換価処分を行います。
(例:従業員の解雇、契約関係の整理など)
破産管財人が財産状況や換価の進捗を報告します。
換価が完了次第、債権者への配当が実施されます。
配当が終了すると、裁判所は破産手続終結決定を行います。
配当すべき財産がない場合は、異時廃止決定(破産法第217条)となります。
これにより会社の法人格が消滅します。
民事再生の大まかな流れは、次のとおりです。
弁護士に依頼し、申立書類を準備します。
同時にスポンサー企業の選定やM&Aの検討を進めます。
裁判所に民事再生手続開始の申立てを実施します。
予納金の納付も行います。
裁判所は必要に応じて保全処分を発令します。
監督委員を選任します。
裁判所が再生手続開始決定を行います。
債権届出期間、債権調査期間の設定が行われます。
会社(清算型の場合は管財人)が再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
清算型の場合、財産の処分方法や配当計画を記載します。
債権者集会で再生計画案の決議を実施します。
議決権者の過半数かつ議決権総額の2分の1以上の同意が必要です。(民事再生法第172条の3)
債権者集会で承認がされた後、裁判所が再生計画を認可します。
再生計画に従って、債務の履行を行います。

最後に、会社をたたむ際に実務上留意すべきポイント3点を解説していきます。
会社をたたむ際、まず重要な点の1つは「いかに価値を残すか」という視点です。
廃業を決断する前に、自社の事業や資産の価値を客観的に評価することが重要です。
たとえ赤字企業であっても、以下のような価値が存在する場合があります。
技術力やノウハウ
顧客基盤や取引関係
ブランドや許認可
優秀な人材
立地の良い不動産
これらは第三者にとって価値があり、M&Aや事業譲渡により現金化できる可能性があります。
近年ではM&A仲介のプラットフォームの活用も拡大しており、中小企業庁の「中小M&Aガイドライン」(2023年改訂、第2版)では、M&Aを事業承継の有効な選択肢として位置づけています。
事業譲渡や株式譲渡により、従業員の雇用を維持しながら、経営者は譲渡対価を得ることができます。
特に、黒字廃業を検討している企業の場合、M&Aにより企業価値を現金化できる可能性が高くなります。
帝国データバンクの調査によれば、2022年のデータとして黒字での休廃業をした企業が54.9%であり、過去最低の数値ではあるものの、半数以上が黒字廃業であることが分かります。
これらの企業が持つ経営資源を次世代に引き継ぐことは、社会的にも意義があるでしょう。
出典:帝国データバンク|全国企業「休廃業・解散」動向調査(2022年)
また、M&Aが困難な場合でも、計画的に資産を処分することで、清算時の費用を確保し、債権者への弁済原資を作ることができます。
不動産、設備、在庫などを市場価格で売却するには、時間的余裕が必要です。
急いで処分すると二束三文になってしまうため、早期の準備が重要です。
M&Aを検討する場合、買い手企業は必ずデューデリジェンス(企業調査)を実施します。財務、法務、労務、事業面など多角的な調査が行われるため、主に以下の準備が必要です。
対象事項はこれら以外にも多々ありますが、デューデリジェンスで問題が発覚すると、譲渡価格の減額や取引の中止につながります。日頃から適切な会計処理と書類管理を行うことが重要です。
また、M&Aの契約では、売り手が会社の状況について表明保証を行います。虚偽の表明があった場合、契約後でも損害賠償責任を負う可能性があります。不明な点や懸念事項は、必ず買い手に開示することが重要です。
M&Aや事業承継を進める際、従業員や取引先への適切な対応が不可欠です。情報開示のタイミングや方法を誤ると、優秀な人材の流出や取引先との関係悪化を招きます。 中小企業基盤整備機構の「事業承継支援マニュアル」では、ステークホルダーへの丁寧な説明と理解の獲得が重要であると指摘しています。特に従業員に対しては、雇用の継続や労働条件の維持について明確に説明することが求められます。
出典: 中小企業基盤整備機構「事業承継支援マニュアル」
「経営者保証に関するガイドライン」は、2013年12月に日本商工会議所と全国銀行協会が策定した自主的なルールです。中小企業の経営者が金融機関からの借入に際して提供する個人保証について、適切な保証契約の在り方を示しています。
具体的には、経営者保証が企業融資における標準的な手段として用いられるよりも、補充的に活用されるようにするための指針として位置づけられます。例えば、停止又は解除条件付きの保証契約、流動動産譲渡担保、近時では企業価値担保権なども注目されますが、むしろ代替的に経営者保証を位置づけ、経営者保証に依存しない事業融資のあり方を志向するものです。
参照:一般社団法人全国銀行協会|『経営者保証に関するガイドライン』平成25年12月
ガイドラインの主な内容は次のとおりです。
特に会社の破産手続きにおいて、経営者保証ガイドラインを活用することで、以下のメリットがあります。
全国銀行協会の報告によれば、経営者保証に依存しない融資の実績として、2024年度においては、平均値として政府系金融機関で56%、信用保証協会で53%、民間金融機関において34%となっており、いずれも増加傾向にあることが報告されています。
出典:中小企業庁|経営者保証 3.政府系金融機関及び信用保証協会におけるガイドラインの活用実績
経営者保証ガイドラインを活用するには、以下の条件を満たす必要があります。
日頃からこれらの条件を満たすよう経営することで、万が一の際にガイドラインの活用が可能となります。 また、実際にガイドラインを活用する際は、中小企業再生支援協議会や認定支援機関など専門家のサポートを受けることが重要です。金融機関との交渉では、専門家の助言に基づいて進めることで、より良い条件での合意が期待できます。

会社をたたむという決断は、経営者にとって非常に重い選択です。しかし、適切な方法を選び、計画的に進めることで、従業員や取引先への影響を最小限に抑え、経営者自身の将来も守ることができます。
会社をたたむ手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。タイミングを誤ると選択肢が限られてしまうため、早期に弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
特に以下のような状況では、すぐに専門家への相談が必要です。
企業法務弁護士ナビでは、事業承継や企業再生、倒産手続に詳しい弁護士を多数掲載しています。初回相談無料やオンライン面談対応など、こだわりの条件を指定して検索することができるので、 まずは弁護士を探してみるところから始めてみましょう。
 編集部
編集部
本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。
※企業法務弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
