弁護士とマッチングできます
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。

生成AIの急速な普及により、誰もが簡単に高品質なイラストを作成できる時代が到来しました。
しかし、その利便性の裏側では、著作権をめぐる複雑な法的問題が次々と浮上しています。
「AIが学習したデータの著作権は?」「AI生成物に著作権は認められるのか?」「商用利用しても大丈夫なのか?」——これらの疑問は、クリエイター、AI開発事業者、企業の法務担当者など、あらゆるステークホルダーにとって喫緊の課題となっています。
実際に、海外では大規模な集団訴訟が提起され、国内でも権利侵害を主張する声が高まっています。
文化庁は2024年に「AIと著作権に関する考え方について」を公表しましたが、依然としてグレーゾーンは広範に残されており、実務上の判断に迷うケースが後を絶ちません。
本記事では、AIイラストをめぐる著作権の全体像を基礎から実務まで網羅的に解説します。
単なる法理論の解説にとどまらず、各ステークホルダーが直面する具体的な課題と、その実践的な対応策まで踏み込んでお伝えします。
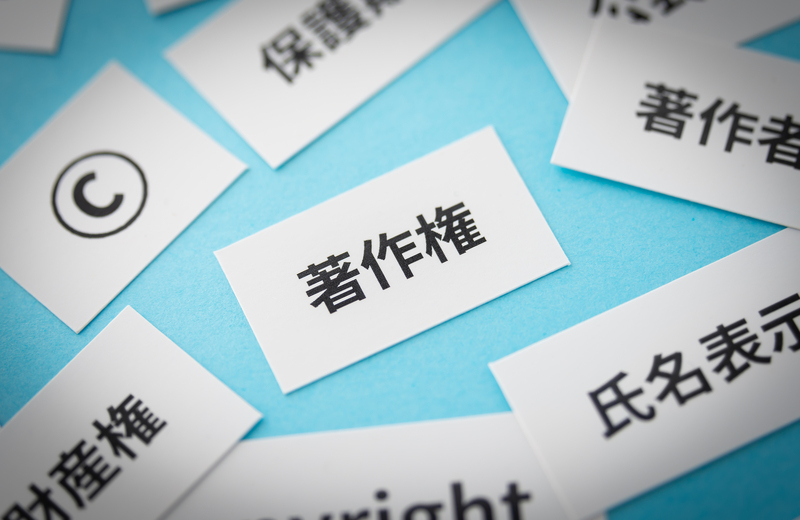
まず、前提となる基礎知識として、著作権とAI生成物の著作物性に関する基本的な考え方を解説していきます。
著作権法第2条第1項第1号では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。
この定義から、著作物として保護されるためには以下の要件を満たす必要があります。
イラストは、「文芸」あるいは「美術の著作物」の一環として保護されます。
ここでポイントとなるのが「創作性」の要件です。創作性は「作者の個性の表れ」があれば足り、高度な芸術性や独創性までが求められるわけではありません。
AI生成物の著作物性については、「人」による創作物であるといえるかどうか、すなわちAIに一定の指示文(プロンプト)を入力するなどしてAIから出力を得た人による創作物であるといえるかどうかということが論点となります。
文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」(2024年)によれば、AI生成物が著作物として保護されるかは、AIが自律的に作成したものであるか、人が思想感情を創作的に表現するための道具として使用したものであるかという点により判断されます。
具体的には、人間の創作意図及び創作的寄与の有無によって判断されます。
参照:文化審議会著作権分科会法制度小委員会|AIと著作権に関する考え方について(2024年3月15日)
実務上の判断基準としては、「人間がどの程度創作的な判断をしたか」が重要です。プロンプトの入力だけでなく、生成過程での選択・調整、生成後の編集など、総合的に人間の創作性を評価します。
仮にAI生成物に著作物性が認められる場合、その著作者は「創作的寄与をした人間」となります。AIそのものは法的な権利主体となり得ないため、AIツール開発者ではなく、実際にAIを使って創作した人が著作者となるのが原則です。
ただし、これは利用規約によって、異なる場合があります。後述するように、ツールによっては生成物の権利帰属について独自の規定を設けているため、必ず確認が必要です。
著作権法は、著作物に対して複数の権利メニューを定めています。そのうち、AIイラストに関連する主要な権利は以下の通りです。
著作財産権
著作者人格権
AIイラスト生成の文脈では、特に以下の権利が問題となります。

AIイラスト生成ツールは多数存在しますが、それぞれ利用規約や著作権の取扱いが異なります。ここでは代表的なツールの規約を比較し、実務上の注意点を解説します。
| ツール名 | 生成物の権利帰属 | 商用利用 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| Canva | 原則ユーザーに帰属 | 有料プランで明示的に許可 | Canva提供の素材を使用した部分はCanvaがライセンスを保持。権利関係が複雑になる可能性あり。 |
| Midjourney | 有料プラン加入を条件に、適用法の下でユーザーに帰属 | 有料プランで可能 | 年間売上100万ドル以上の企業は「Pro」以上のプランが必要。無料トライアルは現在提供なし。 |
| DreamStudio (Stable Diffusion) | ユーザーの属地法に基づき、ユーザーに帰属(モデルライセンスは権利主張を放棄) | モデルライセンス上は可能 | サービス(DreamStudio)とモデル(Stable Diffusion)で法的枠組みが異なる。準拠法が米国カリフォルニア州法。 |
| MyEdit | CyberLinkに帰属 | 原則として個人利用目的のみ許諾(商用利用は許諾外) | ユーザーではなく運営会社に権利が帰属する点が他のツールと大きく異なるため要注意。 |
Canvaは、デザインプラットフォームとして広く利用されており、AI画像生成機能も提供しています。テンプレートベースの使いやすさが特徴で、ビジネス用途での利用が多いツールです
Canvaの利用規約では、AI生成コンテンツについて以下のように定めています。
参照:Canva|AIサービスに関する利用規約, Canva’s Content License Agreement
Canvaは比較的権利関係が明確で、商用利用のハードルが低いツールです。ただし、テンプレートや素材を組み合わせた場合、その権利関係が複雑になる可能性があるため、完全オリジナルのAI生成部分と既存素材部分を明確に区別することが重要です。
Midjourneyは、高品質なAIイラスト生成で知られるツールです。Discord経由で利用する特徴的なインターフェースを持ち、アーティスティックな表現に優れています。
Midjourneyの利用規約(Terms of Service)は以下の点が特徴的です。
・権利帰属の基本原則: 基本的に、生成物の権利について、適用法のもとにおいて完全な権利を取得することとされています。
You own all Assets You create with the Services to the fullest extent possible under applicable law.
・企業利用の条件: 年間売上100万ドル以上の企業またはその従業員の場合、アセットを所有するには「Pro」または「Mega」プランへの加入が必要です。
If you are a company or any employee of a company with more than $1,000,000 USD a year in revenue, you must be subscribed to a 'Pro' or 'Mega' plan to own Your Assets.
・他者の画像の取扱い: 他者の画像をアップスケールした場合、それらの画像は元の作成者が所有権を保持します。
If you upscale the images of others, these images remain owned by the original creators.
・所有権の継続性: 作成したアセットの所有権は、その後メンバーシップをダウングレードまたはキャンセルした場合でも存続します。
Your ownership of the Assets you created persists even if in subsequent months You downgrade or cancel Your membership.
参照: Midjourney Terms of Service
※現在、Midjourneyは無料トライアルプランを提供しておらず、すべてのユーザーは有料プランへの加入が必要です。
Midjourneyの場合、有料プランの中で、かつユーザーに対する適用法の下において許容される範囲内で、AI生成物についてユーザーに権利帰属するものとされます。
DreamStudioは、Stable Diffusionを開発したStability AIが提供する公式インターフェースです。オープンソースモデルを基盤としており、技術的な柔軟性が高いのが特徴です。
前提として、Stable Diffusionのモデルライセンスでは、AIモデルを提供するStability.ai側が権利主張を放棄しているため、ユーザーの属地法を基本としてその適用法の許容する限り、ユーザーへの権利帰属が認められるものとされています。
Except as set forth herein, Licensor claims no rights in the Output You generate using the Model. You are accountable for the Output you generate and its subsequent uses. No use of the output can contravene any provision as stated in the License." (本ライセンスに定める場合を除き、ライセンサーは、ユーザーがモデルを使用して生成した出力に対して権利を主張しません。ユーザーは、生成した出力とその後の使用について責任を負います。出力の使用は、本ライセンスに定められた規定に違反してはなりません)
その上で、DreamStudioの利用規約では、生成物の権利に関する明示的な定めはありません。
You are solely responsible for your use of the Services, including your text prompts, generation of Content, and the consequences of your Content Sharing." (ユーザーは、テキストプロンプト、コンテンツの生成、コンテンツ共有の結果を含め、サービスの使用について単独で責任を負います)
参照: Stability AI Terms of Service, DreamStudio Terms of Service
DreamStudioとStable Diffusionは、サービスとモデルの法的枠組みが異なる点が特徴です。具体的には、次の4つのポイントで整理されます。
上記の諸点に注意して使用する必要があります。
MyEditは、CyberLinkが提供するオンライン画像編集ツールで、AI生成機能を含む多様な編集機能を統合しています。日本語対応が充実しており、国内ユーザーに使いやすいツールです。
Myeditにおける生成物については、サイバーリンクのコンテンツとされ、ユーザーではなくCyberLinkに帰属するものとされます。一定の個人使用は許諾されていますが、商用利用などは許諾外にあると考えられるため、利用の際は注意が必要です(規約9のⅠ)。
参照: https://jp.cyberlink.com/stat/policy/jpn/tos.html

AIイラストをめぐる著作権紛争は、国内外で急増しています。ここでは実務上重要な示唆を含む3つの事例を紹介します。
2023年1月、米国カリフォルニア州で、アーティスト3名がStability AI、Midjourney、DeviantArtを相手取り、集団訴訟を提起しました。原告らは、自身の著作物が無断でAIの学習データとして使用され、それによって自分たちの画風を模倣した画像が生成可能になったと主張しています。
2024年8月12日、カリフォルニア州北部地区連邦地裁のWilliam Orrick判事は重要な判断を示しました。裁判所は、訴訟の一部請求を却下しましたが、直接的な著作権侵害の請求については訴訟の継続を認めました。特に、裁判所はアーティストらが「Stable Diffusionが著作権で保護された作品に大きく依存して構築され、意図的に侵害を促進するように設計された」と合理的に主張していると認定しました。
2025年10月現在、最終判決はまだ下されておらず、訴訟は証拠開示(ディスカバリー)段階にあります。
2024年8月、作家3名が、Anthropicが海賊版サイトから700万冊以上の書籍を違法にダウンロードし、AIモデル「Claude」の訓練に使用したとして訴訟を提起しました。カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所のウィリアム・アルサップ判事は、合法的に購入した書籍でAIをトレーニングすることは「変容的利用(transformative use)」に該当し、フェアユースとして著作権侵害にはあたらないという画期的な判決を下しました。
裁判所はLLMの学習プロセスを「本質的に変形的」と評価しました。
2025年9月、Anthropicは15億ドル(約2200億円)の和解金を支払うことで合意しました。これは米国著作権訴訟史上最大の和解金額とされています。
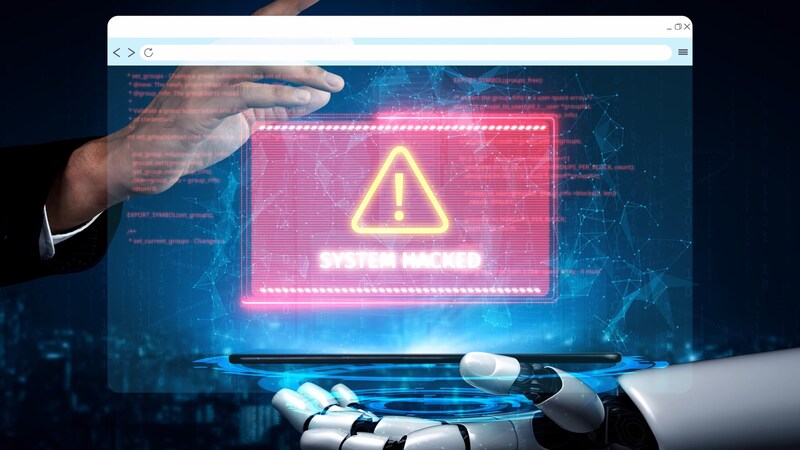
AIイラストの利用において最も重要な実務的問題が、著作権侵害の成否判断です。具体的なケーススタディを通じて、侵害となる場合とならない場合の境界線を明確にします。
AIイラストが著作権侵害となるのは、既存著作物の複製権または翻案権を侵害する場合です。以下、具体的なケースを見ていきます。
最も明確な侵害ケースは、AI生成物が既存のイラストと実質的に同一または酷似している場合です。
【具体例】
判断基準としては、「既存著作物の表現上の本質的特徴を直接感得できるか」という複製権侵害の一般的な基準が適用されます。
次に、既存著作物を基にしつつ、新たな創作性を加えた場合でも、元の著作物の表現上の本質的特徴が維持されている場合は翻案権侵害となります。
【具体例】
翻案の判断は、元の著作物の「表現上の本質的特徴」が新作品から直接感得できるかがポイントです。
そのほか、パブリシティ権・肖像権侵害として、著作権以外の権利侵害にも注意が必要です。実在の有名人の容姿を無断でAI生成し商用利用する場合などが該当します。
著作権法は「表現」を保護するものであり、「アイデア」や「画風」自体は保護されません。
【具体例】
ただし、「◯◯(特定作家名)風」というプロンプトで、結果的に作風を超えて表現上の特徴を再現してしまった場合は、侵害となる可能性があります。
既存著作物を参考にしても、十分な創作的要素を付加し、元の著作物の本質的特徴が感得できなくなった場合は侵害とはなりません。
保護期間が満了した著作物(パブリックドメイン)を基に生成する場合は、原則として自由に利用できます。

ここからは、主なステークホルダーごとに、実務上注意すべきポイントを解説していきます。まず、AI開発者が留意すべきポイントです。
AI学習における最大のリスクの一つが、特定の著作物やスタイルに偏ったデータセットの使用です。学習データが偏ると、生成物が特定の既存著作物に類似しやすくなり、著作権侵害リスクが高まります。
実務的対応策として、まずデータセットの多様性確保が重要です。様々な時代、地域、スタイルのイラストをバランスよく収集し、特定作家の作品数に上限を設定します。学習データや教師データ側のチューニング処理により、データセット構築の際に学習のアルゴリズムの設計において希釈化を図ることで、特定の著作物に対する依拠性・類似性が惹起されるリスクを低減できます。
さらに、著作権者からの削除要請に対応する除外リスト(オプトアウト)の整備も不可欠です。
AI学習において、海賊版サイトや違法アップロードされたコンテンツを学習データとして使用することは、重大な法的リスクを伴います。
著作権法30条の4但し書きは「著作権者の利益を不当に害する場合」を例外としており、海賊版からの学習はこの例外に該当する可能性が高いと考えられます。結果として、学習目的であっても複製権侵害となるリスクがあります。
実務的対応策として、データ収集源の厳格な管理(ホワイトリスト/ブラックリスト作成)、メタデータによる出所追跡、画像ハッシュ値による海賊版データベースとの照合などが必要です。
RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、外部データベースから関連情報を検索し、それを基にAIが回答を生成する技術です。RAG機能は、学習済みモデルに加えて、リアルタイムでの著作物の利用を伴うため、通常のAI生成とは異なる法的考慮が必要です。
実務的対応策として、データベースの権利クリアランスが重要です。参照用データベースに収録する著作物のライセンス取得や、ユーザーに対する参照元情報の開示など、透明性の確保が求められます。この技術は比較的新しいため、法的解釈が確立しておらず、専門家と連携し保守的な運用を心がけることが重要です。

次に、AIツールを使ってイラストを制作・販売するクリエイターの実務上重要な留意事項です。
AIクリエイターが直面する最大の法的課題は、生成物の著作物性確保です。前述の通り、AI生成物が著作物として保護されるには、人間の創作的意図及び客観的寄与が必要です。
単純なプロンプト入力だけでは、人間の創作的寄与が不十分と判断されるリスクがあります。
以下のようなフィードバックプロセスを経ることで、創作性が認められやすくなります。
複数の要素を組み合わせた独自の設計、スケッチやラフ案の作成を行います。
商用利用では、さらに実践的アプローチとして、次のような施策が考えられます。
制作過程の可視化
品質管理基準の設定
付加価値の明確化
プロンプトの内容は、著作権侵害リスクと創作性の両面で重要です。
適切なプロンプト設計により、リスクを低減しつつ創作性を高めることができます。
ここでは、具体性と抽象性の両面を効果的に活用することがポイントです
まず、過度に具体的なプロンプト(特に既存作品への言及)は、著作権侵害リスクを高めます。次のような例が挙げられます。
リスクを低減した抽象的表現として、「ファンタジー世界の勇敢な騎士」「柔らかな水彩タッチの風景画」「温かみのある色調の日常シーン」などが推奨されます。
一方、抽象的すぎるプロンプトでは創作性の主張が困難になります。
以下のように、既存作品に依存しない形で具体性を加えます。
全体のフローとしては、抽象から具体へと段階的にプロンプトを発展させることです。
「幻想的な森の風景」
「夜の森、月明かりが差し込む神秘的な雰囲気」
「巨大な古木が立ち並ぶ森、月光が木々の間から地面を照らし、光る苔が育っている。青と紫を基調とした色彩」
「苔の数を増やし、もっと幻想的に」
「木の質感をよりリアルに」
使用するAIツールによって、生成物の権利帰属や商用利用の可否が大きく異なります。用途に応じた適切なツール選択は、法的リスク管理の基本です。
選択基準のチェックリストとして、次のようなポイントが挙げられます。
① 利用規約の明確性
② ライセンス形態
③ 学習データの透明性
④ サポート体制
用途別の推奨アプローチとして、個人的な創作・学習目的では無料プランでも比較的自由度が高いツールを選択し、多様なツールを試して自分に合ったものを見つけ、学習データの出所にはそれほど神経質にならなくてよいでしょう。
商用プロジェクト・クライアントワークでは必ず有料プランで商用利用が明示的に許可されているツールを使用し、企業規模による制限がないか確認し、生成物の権利が完全にユーザーに帰属するツールを優先します。
さらに、パブリックな発表・コンテスト応募では規約でパブリックな利用が許可されているツール、著作権侵害リスクが低いツール(学習データが適法)、生成物の独自性を主張しやすいツールを選択するようにしましょう。
実務上は、目的に応じて複数のツールを使い分けることが効果的です。
アイデア出し段階では無料ツールで多様な案を生成し、ブラッシュアップ段階では有料ツールで品質向上し、最終調整では画像編集ソフトで人間が仕上げます。
ただし、この場合も各ツールの規約を確認し、生成物の組み合わせ利用が許可されているか確認が必要です。
規約変更への対応として、AIツールの利用規約は頻繁に変更されます。
定期的な規約の再確認(少なくとも四半期に1回)、規約変更通知への注意、重要プロジェクトでは開始時点の規約を保存、規約変更が不利な場合の代替ツールの検討が重要です。

イラスト等の現著作者・クリエイター側が、AIによる著作権侵害に対して対応し、自分の権利を保護するために、次のようなポイントに留意すべきです。
日本の著作権は「無方式主義」を採用しており、創作と同時に自動的に権利が発生します。
しかし、権利の存在や帰属を明確にするため、任意の登録制度が用意されています。
著作権登録(文化庁)には複数の種類があります。
実名の登録(第75条)として変名やペンネームを使う著作者が実名を登録できます。
第一発行年月日等の登録(第76条)として著作物の公表時期を公示できます。
著作権譲渡等の登録(第77条)として権利移転の事実を公示できます。
プログラム著作物の登録(ソフトウェア情報センター)はイラストには直接関係しませんが、AIモデル開発者にとっては重要です。
AI時代における登録のメリットとして、創作時期の証明ではAI生成物との前後関係を明確化し、「どちらが先か」の立証が容易になります。
権利帰属の明確化では共同制作の場合の権利関係の公示、譲渡の有無の明確化ができます。
訴訟における証拠力として、登録事項は推定力を持ち(反証がない限り真実と推定)、立証負担の軽減につながります。
登録制度以外にも、次のような手段が実務上有効なものとして挙げられます。
・タイムスタンプの活用
・電子透かし・メタデータの埋め込み
・作品データベースへの登録
実務的な活用フローとして、作品完成時にタイムスタンプ取得、重要作品は文化庁に登録申請、電子透かし・メタデータを埋め込んで公開、定期的に自作品のAI利用状況をモニタリング、侵害発見時は登録証明を活用して権利主張というステップを踏みます。
近年、クリエイターの中にはオープンソースライセンス(特にCreative Commons)で作品を公開する動きがあります。
これにはメリットとデメリットの両面があります。
オープンソース化のメリットとして、作品の拡散・認知度向上、ファンコミュニティの形成、二次創作の促進による作品世界の拡大、教育・研究目的での利用促進が挙げられます。
ライセンス・ロイヤリティ設定が担保されているプラットフォームでは、正当な収益化が可能です。
一方、AI時代における特有のデメリットとして、AI学習データとして自由に利用される可能性、独占的な商業利用の機会喪失、ライセンス条件の変更や撤回の困難さ、意図しない用途での利用(AIによる大量生成など)があります。
独占権を保持するのか、オープンソース化してライセンス設定をするべきかの判断ポイントは、下記のように整理することができます。
Creative Commonsライセンスを選択する場合でも、適切なライセンスを選択することで一定の権利保護が可能です。
CC BY-NC-ND(非商用・改変禁止、AI学習への利用も改変に該当する可能性)、CC BY-NC(非商用のみ、商用AI学習を制限)、CC BY-SA(同一ライセンス継承、AI生成物も同じライセンスで公開が条件)などがあります。
オプトアウト表明の重要性として、AIによる学習を望まない場合、明示的にその旨を表明することが重要です。
作品への明記(「AI学習利用不可」の表示)、robots.txtやnoaiタグの活用、AI開発企業へのオプトアウト申請、業界団体を通じた権利保護の声明などの方法があります。
AIの普及は脅威である一方、適切な権利設定により新たな収益機会も生み出します。
ライセンスビジネスの展開として、次のようなバリエーションがあります。
AI開発企業への学習データとしてのライセンス供与
データセット提供企業との契約
自身の画風を再現したAIモデルの公式版を作成
ライセンス料と引き換えに利用許可
AI企業との共同開発
公式コラボレーションによるレベニューシェア戦略
ロイヤルティ設定に際しては、対価の算定基準を明確にする必要があります。
学習データとしての利用ではデータ量・品質に応じた一時金、生成物の利用では生成回数・売上に応じた従量課金、ブランド使用では固定ロイヤルティと変動ロイヤルティなどを選択、あるいは組み合わせるのが有効です。
また、契約条件の設定として、利用範囲の限定(地域、期間、用途)、品質管理条項(生成物の品質基準)、監査権の確保(利用状況の定期的な確認)を定めることが有効でしょう。
技術的保護措置との連携として、DRM(デジタル著作権管理)技術の活用、ライセンス管理システムの導入、不正利用の検出・追跡機能を実装します。
AI企業との契約交渉では、複数の重要ポイントがあります。
学習データとしての利用条件では、使用目的の明確化(特定モデルのみか、全社的利用か)、再許諾の可否(第三者への提供を認めるか)、学習後のデータ保持期間を定めます。
新たなビジネスモデルの可能性として、創造的なアプローチもいくつか考えられます。
オリジナル作品のNFT化による希少性確保
ユーティリティトークンの設計による⼩売チャネルとのタイアップ
スマートコントラクトによる⾃動ロイヤルティ分配
AI企業とのジョイントベンチャー設⽴
収益を分配しながら共同でブランド育成
原著作者がこれらの実務ポイントを活用することで、AI時代においても自身の権利を適切に保護しつつ、新たな収益機会を獲得することが可能になります。

AIイラストと著作権の問題は、単なる法的リスクの管理にとどまらず、創造性と技術革新の調和をいかに実現するかという、より本質的な課題を私たちに突きつけています。
法的な枠組みを理解し遵守することは大前提ですが、それだけでは不十分です。クリエイターの権利を尊重し、技術の可能性を最大限に活かし、そして社会全体に価値を提供するという、三者のバランスを常に意識することが重要です。
グレーゾーンが多く存在する現状では、法的リスクを恐れるあまり萎縮するのではなく、適切なリスク管理のもとで新たな価値創造に挑戦する姿勢が求められます。
AIと著作権をめぐる環境は今後も急速に変化し続けます。本記事の内容は現時点(2025年10月)での法的状況と実務的知見をまとめたものですが、常に最新情報をアップデートし、状況に応じた柔軟な対応が必要です。
重要な判断に迷う場合や、具体的な案件で法的リスクが懸念される場合は、必ず知財専門の弁護士など専門家に相談することをお勧めします。
企業法務弁護士ナビでは、AIイラストと著作権に関する問題に詳しい弁護士を掲載しています。初回相談無料やオンライン面談対応など、こだわりの条件を指定して検索することができるので、 まずは弁護士を探してみるところから始めてみましょう。
