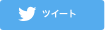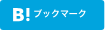「他社へ商標権を譲渡する/譲渡してもらう」という場面では、商標権譲渡契約書を交わすのが一般的です。
契約は口約束でも可能ですが、「言った言わない」などのトラブルとなった場合、契約内容を証明することが困難になります。そのような事態を回避するためにも、契約時は必ず契約書を作成しておきましょう。
またただ契約書を交わすだけでは商標権は移転しないため、別途登録手続きが必要です。このことを抑えておかないと、契約書をかわしたのにも関わらず、商標権譲渡に関するトラブルが発生し、会社に大きな損を与える恐れがあります。
この記事では、商標権譲渡契約書の作成方法や注意点、商標権の移転方法や弁護士に相談するメリットなどを解説します。
商標権譲渡契約書の作成方法
適切に譲渡対応を済ませるためにも、契約書を作成する際は最低限の事項を押さえておく必要があります。ここでは、商標権譲渡契約書の記載事項・雛形・費用などについて解説します。
記載事項
契約書作成にあたっては、譲渡範囲・対価・支払方法・支払期限・移転登録対応などの条項は記載しておきましょう。また譲渡方法としては、権利すべてを譲渡する「全部譲渡」のほか、指定商品・指定サービスが複数ある場合は、譲渡範囲を指定して「一部譲渡」とすることもできます。
雛形
作成形式について特に細かい決まりはありませんが、一例を紹介すると以下の通りです。
|
商標権譲渡契約書 A社(以下「甲」)とB社(以下「乙」)は、○○の商標権譲渡について、以下の通り契約(以下「本契約」)を締結する。 第1条(商標権譲渡) 甲は、下記の商標権(以下「本商標権」)について、乙に譲渡する。 1.商標登録 第○○○○○号 2.商品の区分 第○類 3.指定商品 ○○ 第2条(対価) 乙は、本契約における譲渡対価として、○○万円(税込み)を令和○○年○月○日までに、甲の指定銀行口座へ振り込む方法によって支払う。 第3条(移転登録の手続き) 甲は、第2条で定める対価の受取と引き換えに、本商標権の移転登録および名義変更のために必要な書類を収集し、交付しなければならない。 第4条(保証) 甲は、本商標権にかかる使用権について、第三者へ許諾していないことを保証する。 2.甲は、本商標権について、第三者が侵害している事実はないことを保証する。 3.甲は、本商標権について、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証する。 第5条(解除) 乙が、第2条で定める対価の支払いを怠った場合、甲によって債務履行が請求されたのち履行されなければ、本契約について解除できる。 2.前項のほか、相手方が本契約の各条項に違反した場合、本契約について解除できる。 第6条(裁判管轄) 甲および乙は、本契約について紛争が発生した場合、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所にすることを合意する。 第7条(協議事項) 本契約で規定していない事項や、規定事項に関する解釈で疑義が発生したものについては、その都度協議を行って解決するものとする。 本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各1通ずつ保有するものとする。 令和○○年○月○日
甲 (住所)○○ (会社名)株式会社○○ (代表者氏名) ○○
乙 (住所)○○ (会社名)株式会社○○ (代表者氏名) ○○ |
費用
契約書には収入印紙を貼り付ける必要があり、契約金額に応じて以下のように印紙税がかかります。
|
記載された契約金額 |
印紙税額 |
|
1万円未満 |
非課税 |
|
1万円以上10万円以下 |
200円 |
|
10万円を超え50万円以下 |
400円 |
|
50万円を超え100万円以下 |
1,000円 |
|
100万円を超え500万円以下 |
2,000円 |
|
500万円を超え1,000万円以下 |
1万円 |
|
1,000万円を超え5,000万円以下 |
2万円 |
|
5,000万円を超え1億円以下 |
6万円 |
|
1億円を超え5億円以下 |
10万円 |
|
5億円を超え10億円以下 |
20万円 |
|
10億円を超え50億円以下 |
40万円 |
|
50億円を超えるもの |
60万円 |
|
契約金額の記載がないもの |
200円 |
商標権譲渡契約書を交わす際の注意点
トラブルなく譲渡対応を済ませるためには、何点か確認しておくべき事項があります。ここでは、契約書対応にあたって、譲渡側・譲受側それぞれの注意点について解説します。
譲渡側の注意点
譲渡側については、主に以下の3点を確認しましょう。
|
・譲渡後の権利阻害に関する条項が記載されているか ・対価・支払い期限・支払い方法が明確であるか ・第三者への再譲渡・使用許諾の許否が明確であるか |
譲渡後の権利阻害に関する条項が記載されているか
商標権を譲渡する際は、「譲渡後の商標利用にあたって権利侵害が生じないか」という点を注意しましょう。例として「譲渡する商標と類似した商標を有しており、今後も使用したい」という場合は、以下のように「類似商標の使用に関する条項」を契約書に記載しておく必要があります。
|
記載例1:本契約締結後、甲(譲渡人)がこれまで通り類似商標を使用することについて、これを妨げることはできない。 記載例2:乙(譲受人)には、譲渡した商標にかかる指定商品について、混同防止表示(出所の混同を避けるために表示を付すこと)を義務づける。 |
そのほか「商標権の一部譲渡を行い、自社に残った指定商品については今後も販売したい」という場合などは、以下のように「指定商品の販売に関する条項」を契約書に記載しておく必要があります。
|
記載例:本契約締結後、甲(譲渡人)がこれまで通り指定商品を販売することについて、これを妨げることはできない。 |
対価・支払い期限・支払い方法が明確であるか
商標権は、対価と引き換えに譲渡するのが通常です。しかし場合によっては、「予定通りに支払ってくれない」などのトラブルとなる可能性もゼロではありません。契約書を交わす際は、「いくら・いつまで・どのように」などの対価事項について、明確に記載しているか確認しましょう。
第三者への再譲渡・使用許諾の許否が明確であるか
なかには、譲渡後に商標権が第三者へ再譲渡されたり、使用許諾が行われたりすることもあります。ただし、自社と関わりのない第三者へと商標権が移転した場合、これまでのブランドイメージが損なわれてしまう恐れもあります。
そのような事態を懸念される場合は、以下のように「第三者への権利移転に関する条項」を契約書に記載しておく必要があるでしょう。
|
記載例:本商標権について、第三者への再譲渡および使用許諾を禁止する。 |
譲受側の注意点
譲受側については、主に以下の3点を確認しましょう。
|
・商標権は有効か ・他社の商標権に抵触していないか ・譲渡側に「商標権移転のための書類対応」が義務付けられているか |
商標権は有効か
商標権の譲渡を受ける際は、「その商標が有効に存在しているのか」という点を確認しておきましょう。その際は、以下のような「商標登録原簿」を特許庁から取得することで確認できます。
引用:原簿について|特許庁
なお「商標権が3年以上使用されていない」というケースについては、「不使用取消審判」を申し立てることもできます。特許庁にて請求手続きを行い、双方の主張を述べたのち取消が認められることで、その商標権は消滅します。不使用期間が長い場合は、選択肢の一つとして考えても良いでしょう。
他社の商標権に抵触していないか
場合によっては、「譲渡を受けた商標権が、ほかの権利に抵触している」というケースも考えられます。そのような事態を避けるためにも、契約にあたっては「譲渡される商標権はそのまま使用可能かどうか」について、事前に調査・チェックを行っておくべきでしょう。
譲渡側に「商標権移転のための書類対応」が義務付けられているか
詳しくは「商標権譲渡契約書後に必ず行う手続き」にて後述しますが、商標権が移転するには書類提出などの登録対応が別途必要となります。スムーズに移転対応を済ませるためにも、譲渡側に対して、以下のような「移転登録にかかる書類対応を義務付ける条項」が契約書に記載してあるか確認しましょう。
|
記載例:甲(譲渡人)は、商標権の移転登録のために必要な書類を交付しなければならない |
商標権譲渡契約書後に必ず行う手続き
商標権が移転するには、商標権譲渡契約書を交わすだけでは不十分であり、特許庁へ書類提出して移転登録手続きを済ませなければなりません。なお手続きにあたっては、「出願後に譲渡するケース」と「登録後に譲渡するケース」で必要書類が異なります。ここでは、商標権が移転するために必要な手続きを解説します。
なお、権利移転までにかかる期間としては、両ケースともに1~2ヶ月程度という場合が多いようです。ただし、個々の申請内容によっては大きく異なることもあるため、目安の一つとして参考にしてください。
出願後に譲渡する手続き
「出願は済んでいるが、まだ登録を受けていない」という場合は、「商標権移転登録申請書」や「譲渡証書」などの書類を提出する必要があります。
商標権移転登録申請書
商標権移転登録申請書とは以下のような書類を指します。なお作成にあたっては、印紙代として3万円がかかります。
引用元:商標権移転登録申請書|特許庁
譲渡証書
譲渡証書とは以下のような書類を指します。
引用元:譲渡証書|特許庁
登録後に譲渡する手続き
「すでに登録が済んでいる」という場合は、「出願人名義変更届」や「譲渡証書」などの書類を提出する必要があります。
出願人名義変更届
出願人名義変更届とは以下のような書類を指します。なお作成にあたっては、印紙代として4,200円がかかります。
譲渡証書
譲渡証書とは以下のような書類を指します。
商標権譲渡契約書を交わす際は弁護士に相談
トラブルなく商標権譲渡を済ませるためには、十分な知識をもった上で契約書を交わす必要があります。あいまいな知識のまま対応してしまうと、以下のような権利トラブルへと発展してしまう場合もあります。
商標Xの権利を有するA社が、携帯電話事業を行うB社と商標権譲渡契約を締結。これによって商標権がB社へ移転したものの、A社は「契約にあたって、『あくまで補足的資料として契約書が必要なだけであり、実際に移転手続きを行うことはない』との説明をB社から受けていた」と主張。
さらに「B社から上記のような虚偽の説明がなければ、本契約について意思表示をしていなかった」として、B社へ移転登録の抹消手続きを請求したという事例です。この事例では、「契約書の記載内容とA社が主張する契約背景のどちらが適用されるのか」という点が一つの争点となりました。
裁判所は、「本契約書の内容から判断すると、移転登録まで予定したものであることが読み取れる上、B社はA社による修正依頼について2度対応している」などを理由に、「A社の主張を裏付けるだけの証拠はない」として、A社の請求を棄却しました。
参考文献:2009WLJPCA02059001
上記のようにトラブルが裁判へと発展した場合、解決するまでには相応の時間と手間がかかります。このような事態を防ぐためにも、まずは弁護士に相談しておくことをおすすめします。弁護士であれば、法的視点から契約書作成・リーガルチェックなどが依頼でき、トラブルなく手続きを進めることができます。
[CTA_property]
まとめ
他社と商標権譲渡契約書を交わす際は、譲渡範囲・対価・移転登録対応・保証など、さまざまな事項を記載しなければなりません。特に「これまで作成したことがない」という方にとっては、大きな手間・労力がかかることが予想されます。
さらに自力で契約書を作成する場合、記載内容に誤りや漏れなどが生じるリスクもあり、場合によっては企業にとって損害が生じる可能性も考えられます。商標権の譲渡にあたって、少しでも不安点を解消するためにも、弁護士に契約書作成やリーガルチェックなどを依頼することをおすすめします。
弁護士に問い合わせる