弁護士とマッチングできます
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。

労働者から不当解雇で訴えられた場合、会社としては目に見えるもの・見えないものも含めて、多大なるコストを支払うことになってしまいます。
そのため企業側としては、労働者から不当解雇で訴えられることを、できる限り防がなければなりません。万が一労働者から不当解雇で訴えられてしまった場合は、弁護士に相談して適切に対応を行いましょう。
この記事では、
などについて解説します。
日本の労働法では、使用者が労働者を解雇するハードルは非常に高くなっています。労働契約法16条に定められる「解雇権濫用の法理」によれば、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない解雇は、解雇権の濫用として無効となります。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。引用元:労働契約法16条
仮に就業規則上の解雇事由・懲戒事由に該当する場合であっても、具体的な事情に照らして解雇が重すぎる処分であると客観的に判断される場合には、使用者は労働者を解雇することはできません。このように、どのパターンの解雇についても、解雇要件は使用者側にとって非常に厳しいものになっています。
したがって、使用者が労働者の解雇を検討する際には、事前に慎重な検討を行うことが大切です。
労働者が使用者に対して、解雇が違法・無効である旨を主張してきた場合には、主に交渉・労働審判・訴訟の3種類の方法によって解雇の有効性が争われます。
それぞれの手続きの概要について見てみましょう。
不当解雇に関する使用者と労働者の争いは、第一義的には交渉によって解決されることが、双方にとって望ましいといえます。話し合いで解決することができれば、時間・労力の観点から、会社にとっては一番傷口が浅く済みます。
また労働者側としても、早期解決できることに越したことはないので、可能であれば交渉で解決したいと考えていることが多いでしょう。なお交渉の段階では、労働者側に弁護士が付いていないことも多いのが実情です。
一度労働者側に弁護士が付いてしまうと、権利主張の内容が強硬化する懸念があります。さらに、交渉が長引けば長引くほど、後述するコストが膨らんでしまうという問題も存在します。そのため使用者側としては、できれば交渉の早い段階で、和解案に合意してしまいたいところです。
仮に労働者が提示する条件がリーズナブルであれば、使用者としては強硬に争うことはせずに、ある程度妥協して受け入れるのが得策になることもあります。
労働審判は、訴訟よりも迅速に労働問題を解決するために設けられた制度です。労働審判では、審理が原則3回以内で終結します。
訴訟の場合は1か月に1回程度の期日が際限なく続いていくことを踏まえると、労働審判による早期解決のメリットは大きいといえるでしょう。労働審判の場合、実質的に会社側が解雇の正当性を論証しなければならないので、訴訟同様に準備の負担は大きいのが難点です。
ただし、労働審判の手続き中では、労働者との間で調停案に合意することもできます。労働審判委員会(裁判官・労働審判員)の提示する調停案が、使用者にとって受け入れ可能な範囲であれば、早い段階での調停成立を目指すことも有効です。
労使が互いに提示する条件がかけ離れている場合は、訴訟に発展して紛争が泥沼化することもやむを得ません。不当解雇事件が訴訟に発展した場合、解決には1年以上かかるケースもあるので、長期戦を覚悟する必要があります。
ただし訴訟手続きの途中でも、裁判官が和解を試みる場面が何度かあります。訴訟の経過を見ながら裁判官の心証を推測して、使用者にとって受け入れもやむを得ないという水準の条件が提示されたら、和解に応じることも検討する価値があるでしょう。
労働者が会社に対して不当解雇を主張してくる場合、労働者が何を考えているかについては、複数のパターンが考えられます。具体的にどのパターンに該当するかの見極めは困難ですが、会社が交渉に臨むうえでは、労働者側の意図をできるだけ正しく把握することも大切です。
以下では、不当解雇を争う労働者側の思考パターンについて解説します。
1つ目は、解雇無効の主張内容のとおり、本当に会社に復職したいと思っているパターンです。復職を希望する理由としては、会社に愛着がある・転職活動に不安があるなど、さまざまなものが考えられます。
労働者が本当に復職したいと思っている場合、上乗せ退職金などの条件を提示しても退職に応じにくい傾向にあります。そのため、使用者側が解雇を維持する場合は、紛争が長期化しやすいのが難点です。
使用者側としては、法的に分が悪い場合には解雇を撤回したうえで、配置転換などの代替手段を模索すべきかもしれません。
2つ目は、基本的には会社に戻りたいと考えているが、上乗せ退職金などの条件が良ければ退職に応じようと考えているパターンです。このパターンの場合、労働者側の考え方も柔軟なので、交渉が比較的成立しやすいという特徴があります。
会社としては、労働者から退職条件の希望を聞いて、会社として受け入れられる範囲の再提案を行っていく方針をとるのが良いでしょう。
3つ目は、解雇無効の主張は交渉材料としての建前に過ぎず、できるだけ良い条件での退職を目指したいと考えているパターンです。このパターンの労働者は、解雇無効の主張をしているものの、最初から会社に戻る気がありません。
つまり、建前と本音が矛盾しているため、労働者側にも交渉上の弱みがあるケースといえるでしょう。会社側の対処法は、前述の2つ目のパターンと基本的には同じです。しかし、「会社に戻る気がない」という労働者の意図が明らかに分かる場合には、解雇の撤回などを匂わせて対抗するのも一つの手段になります。
労働者側としては、解雇を撤回された場合、解雇無効の主張をしている以上はそれに応じざるを得ません。この場合、労働者の真の意図である「好条件での退職」を実現できないのですから、労働者にとっては不本意な結果となります。
労働者に会社に戻る気があるかどうかを見極めるのは難しいですが、口頭やメールベースでの交渉内容を精査して、労働者側の意図を推測しましょう。
不当解雇で労働者から訴えられた場合、会社にはさまざまな方面で多額のコストが生じてしまいます。
具体的に会社に生じるコストは、以下のとおりです。
不当解雇訴訟で会社側が敗訴した場合、労働者に対して損害賠償などの支払いが発生します。どの程度の金額が認められるかはケースバイケースですが、賃金の数か月分から十数か月分程度が相場です。
また訴訟の途中で和解に至った場合でも、判決で認められると思われる支払額に対して、かなりの割合の解決金を支払わなければならないのが通常です。会社としては、全く会社の業務に貢献していない労働者に対して賃金を支払わなければならないのと同じですので、大きな痛手といえるでしょう。
|
解雇の内容 |
解決金相場 |
|
解雇に正当な理由がある |
賃金の1~2ヶ月分程度 |
|
解雇の正当性が否定できない |
賃金の3ヶ月~6ヶ月分程度 |
|
解雇の正当性に相当程度疑義がある |
賃金の6~12ヶ月分程度 |
|
解雇に正当な理由が全くない |
賃金12ヶ月~ |
【参考】労働審判による不当解雇の解決金相場は?解決金を上げるポイントも解説
不当解雇訴訟では、弁護士費用もかなり高額になる傾向にあります。総額で請求額の25%程度に及ぶこともあり、訴訟の結果に関わらず、会社にとっては大きな負担です。なお、交渉や労働審判で解決する場合、訴訟のケースよりも弁護士費用のディスカウントが認められるケースがあります。
具体的な弁護士費用は弁護士によって異なりますので、事件解決の見通しと併せて、弁護士に事前に確認しておくと良いでしょう。
不当解雇訴訟の対応に当たる、法務担当者・人事担当者・上司・同僚などの時間的コストも無視できません。これらの関係者は、会社にとって利益を生まない不当解雇訴訟への対応に、他の業務に充てられたはずの時間を割かなければならないからです。
不当解雇訴訟は、弁護士に依頼する場合であっても、社内の従業員と協力して準備を進めることが不可欠になります。特に関係者を取りまとめる窓口となる担当者については、複雑・面倒な業務が一挙にのしかかってしまいます。
従業員が訴訟対応に時間を取られてしまうと、他の業務がストップしたり、長時間労働により従業員が健康を害したりするリスクが高まります。また、働き方改革の時代に沿った労務コンプライアンスの観点からも、長時間労働の常態化は大いに問題です。
自社の貴重な人材に無駄な時間を費やさせることを防ぐためにも、不当解雇訴訟が泥沼化することは避けるべきでしょう。
前の項目で解説した従業員の時間的コストとも関連しますが、不当解雇訴訟によって従業員の労働時間が伸びた場合、会社にとっては余分な残業代の支払い義務が発生してしまいます。
不当解雇訴訟は会社にとって利益をもたらすものではないため、訴訟対応を原因とする残業代の増加は、会社にとっては純粋なコスト増です。したがって、経営上の合理性の観点からも、不当解雇問題は早期に解決することが望まれます。
上記のように、不当解雇で労働者から訴えられた場合、会社にとっては大きなコストが発生してしまいます。そのため、不当解雇で訴えられることを未然に防げるのであれば、それに越したことはありません。不当解雇訴訟を未然に防ぐための会社側の対策としては、以下のものが考えられます。
日本の労働法上、解雇のハードルは非常に高いので、まずは解雇せずに代替手段を講ずることを検討すべきです。たとえば配置転換によって適材適所の人材活用を模索する方法や、早期退職を募集して解雇せずに人員を削減する方法などが考えられます。
また最終的に解雇を行うとしても、その前段階で代替手段を講じて解雇回避の努力をすることは、法的に大きな意味があります。代替手段を十分に講じた後に、結局解雇せざるを得ないという判断になったとすれば、解雇の正当性を基礎づける事情として働くからです。
上記の理由から、まずは代替手段を検討して、解雇せずに問題状況を改善できないか検討しましょう。
どうしても労働者を辞めさせたい場合には、解雇という形式を避け、合意退職の形で退職を促せないかを検討しましょう。一般的に、会社都合で労働者に対して合意退職を促すことを「退職勧奨」と呼びます。
その際、通常の退職金規程に基づく退職金とは別に上乗せ退職金の支給を提案することによって、労働者側が退職勧奨を受け入れやすくなります。どのくらいの上乗せ退職金を提示すればよいかについては、特に金額相場は決まっておらず、純粋な交渉マターとなります。
したがって会社としては、労働者側の希望額から最低ラインを推測しつつ、徐々に条件を小出しにしながら金額を提示していくことになるでしょう。退職勧奨を労働者が受け入れ、退職の条件に合意した場合には、その内容を退職合意書の形でまとめておきます。
その際、退職合意書の中に紛争の蒸し返し防止に関する条項を入れておけば、後で訴訟などに発展することを防ぐことが可能です。
解雇した労働者から不当解雇で訴えられた場合、会社としてはできるだけ傷口を浅く済ませるためにも、以下の点に留意した対応をとる必要があります。
不当解雇訴訟は準備が非常に大変なので、自社の従業員のみでは通常対応できません。そのため、弁護士費用が掛かることを考慮しても、結局弁護士には依頼せざるを得ないのが実情です。
それならば、早い段階で弁護士に相談することによって、会社として万全の態勢を整えて訴訟に臨む方が良いでしょう。弁護士は、解雇の有効性や労働者側の提案の妥当性などについて、法的な観点から綿密な検討を行います。そのため会社にとっても、法律・実務の相場観を踏まえたうえで、和解交渉・訴訟手続きを進められるメリットがあります。
不当解雇訴訟では、会社は解雇が正当であったことを、複数の証拠を用いて説得的に示さなければなりません。解雇の正当性を基礎づける証拠の具体例としては、以下のものが挙げられます。
会社としては、不当解雇事件が訴訟に発展することを見据えて、交渉段階から上記の証拠を収集・作成・確保するように努めることが大切です。早い段階から訴訟を見据えた対応を行うという観点からは、やはり早期に弁護士に相談することが推奨されます。
不当解雇訴訟を判決まで争った場合、訴訟手続きは1年以上の長期にわたってしまうこともしばしばです。訴訟が長期化すれば、人件費を中心としたコストが膨れ上がり、会社はどんどん悪条件に追い込まれてしまいます。
訴訟手続きの途中の段階で、裁判官の和解提案に応じれば、早期解決により結果的にコストを抑えられます。したがって会社としては、訴訟の場できちんと解雇の正当性に関する主張を展開しつつも、訴訟の展開を見ながら常に和解の可能性を探る姿勢を持っておくことも重要になるでしょう。
不当解雇で労働者から訴えられた場合、会社が負担するコストは、訴訟で負けた場合に支払う金銭だけはありません。それ以外にも、弁護士費用や人件費など、訴訟手続き自体を進めていくための膨大なコストがかかってしまいます。
よって会社としては、できる限り不当解雇問題を訴訟に発展させず、早期解決を目指すことが重要です。弁護士に相談すれば、不当解雇訴訟の予防から実際に発生してしまった不当解雇訴訟への対応まで、企業担当者を全面的にバックアップしてくれます。
万が一労働者から不当解雇により訴えられてしまい、会社としての対応に苦慮している場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
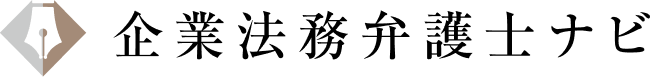 編集部
編集部
本記事は企業法務弁護士ナビを運営する株式会社アシロ編集部が企画・執筆いたしました。
※企業法務弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
