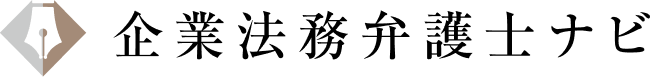従業員(元従業員)からの残業代請求については、会社側に高額の残業代支払義務が認められる可能性もあります。
従業員側の請求が正当なものであればやむなしですが、そうでない場合には会社側は的確に反論しなければなりません。
会社による残業代請求に対する反論にはいくつかのパターンがあります。
これらのパターンを押さえつつ、弁護士と相談をしながら会社としての対応を考えるのが適切でしょう。
この記事では、従業員からの残業代請求に対する典型的な反論のパターンなどについて、法律の専門的な観点から詳しく解説します。
弁護士に問い合わせる
労働者の残業代請求が認められないケース
労働者の残業代請求が法的根拠に基づくものであれば当然支払わなければなりません。ただし、労働者側の請求に法的根拠が伴っていないという場合もあり得ます。
この項目では、労働者側の請求が認められないケースについてご紹介します。
請求された残業代が誤っている場合
労働者側が自ら計算し、請求書を送付してきた場合、計算が誤っていたり、結んでいる労働契約と異なっていたりするケースは少なくありません。
- 固定の割増賃金により支払い済みである。
- 管理監督者であり割増賃金請求の権利がない。
- 労働時間の計算・評価に誤りがある。
会社としては、このような問題がないか十分に吟味しましょう。この段階で弁護士に相談することも検討すべきかもしれません。
時間外労働の対象外となる労働者の場合
取締役など、労働者ではない場合は割増賃金を請求する権利は基本的にありません。また、労働者であっても管理監督者など、経営者と一体的立場にある場合も時間外労働・休日労働の割増賃金を請求することはできません。
ただし、役職上は『管理職』という扱いをしていても、『名ばかり管理職』のように、実態として経営者と一体的立場とはいえない場合は残業代を請求する権利があります。
従業員から残業代を請求された場合の対処法
実際に会社が従業員から未払い残業代を請求されてしまった場合には、法律を踏まえて適切に対処する必要があります。会社が未払い残業代の請求に対処するための方法について、ポイントをいくつか解説します。
労働者からの請求に反論の余地があるか検討する
残業代の計算は、労使で認識の違いが起きやすい問題です。
- 労働者の残業代計算方法は合っているか
- 労働時間の計算は合っているか。
- 労働者に割増賃金を請求する権利があるか
など、十分に吟味し、適切な対応を心がけましょう。精査の結果、労務管理に問題があるようであれば、将来的なリスクを払拭するためにも管理体制の見直しを検討しましょう。
時効が過ぎている賃金がないか確認
残業代の請求権は2年を過ぎると時効消滅します。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
引用元: 労働基準法
労働者からの請求がこの時効期限に対し、適当なものであるかは必ず確認しましょう。なお、残業代の請求権は労働者が退職した後でも有効です。
時効の援用を行う
労働者の残業代請求が消滅時効にかかっている場合には時効の援用を行います。この援用を怠ると、時効消滅している分の未払い残業も支払うことになる場合があります。
労働者からの請求書は放置せず必ず時効を援用しておきましょう。
実際に支払義務のある残業代がいくらかを把握する
まずは、労働者からの残業代請求が会社にとってどのくらいのインパクトを持っているかを確認する必要があります。
そのためには、実際に会社の支払義務が認められそうな未払い残業代がどの程度かを客観的に分析することが必要でしょう。
当然ですが、会社にとって都合の良い事実だけをピックアップして状況を分析しても、会社に生じ得るリスクを正しく分析することはできません。
この場合、従業員からの請求内容と会社側の反論を突き合わせつつ証拠を踏まえるとどの範囲で請求が認められるかどうかという視点での判断が大切です。
残業代の支払いを争うのか、和解に応じるのかを検討する
未払い残業代請求のリスクが客観的に分析できたら、会社として具体的な対応の方針を検討します。
会社側の方針としては大きく分けて、従業員の請求を訴訟手続で争うか、訴訟手続に行く前に和解して終わらせるかの2通りがあります。
従業員側の請求が概ね正当であり、訴訟手続をしても請求額が減じられる可能性が乏しいようであれば、訴訟手続に進む前に和解で終わらせる方がメリットが大きいです。他方、従業員側の請求について、十分に反論の余地があるのであれば、訴訟手続で争う方が良い場合も多いでしょう(訴訟手続で会社側の主張を展開しつつ、最終的に裁判所を交えて和解するというホ言う方もあり得ます。)。
ただし、会社側が従業員からの請求について容易に金銭を支払った場合、その噂が社内に広まってしまう可能性があります。
そうなると、「自分も未払い残業代を請求すれば会社が支払いに応じてくれるのではないか」と期待した他の従業員から、さらなる未払い残業代請求を受けてしまう可能性も懸念されるところです。
このように、会社にとって不利な先例ができてしまうかもしれないことを踏まえて、慎重に和解交渉を数進める必要があるでしょう。
労使の話し合いによる解決を目指す
残業代請求はまずは当事者間の話し合いによる解決を目指しましょう。当事者間で解決が難しい場合は、弁護士などの専門家や労働局などの社外窓口を利用することも検討してください。
会社側の労務に詳しい弁護士に依頼する
会社が従業員からの請求を拒否した場合、高確率で従業員との間で訴訟に発展します。訴訟になることを見据えた場合、早い段階で労務に強い弁護士に相談をしておくことをおすすめします。なお労務を取り扱う弁護士には、従業員側が得意な弁護士と、会社側が得意な弁護士がそれぞれ存在します。
会社側としては、できれば会社側を得意とする弁護士に依頼することが望ましいでしょう。残業代請求訴訟への対応を弁護士に依頼する具体的なメリットについては、次の項目で解説します。
弁護士に問い合わせる
従業員からの残業代請求に対する会社の反論パターン5選
従業員からの残業代請求に対しては、法律上のポイントを踏まえた反論が必要です。
残業代請求に対する会社の反論パターンとして、考えられるものを5つ紹介します。
主張された労働時間が不正確である
従業員の主張する残業時間と、会社が把握している残業時間がズレている場合があります。この場合には、「従業員の主張する労働時間は不正確である」と反論していくことになります。
この場合、労働時間に争いがあることになりますので、従業員側は主張する労働時間を証拠により証明しなければなりません。仮にこの証明が不十分であれば、従業員側で主張する労働時間があったことは認定されず、その請求の全部又は一部は棄却されます。
会社が許可しない残業である
裁判例の傾向に照らすと、従業員が会社からの明示的な残業禁止の指示に反して残業をした場合、その労働時間性が否定される場合があります。
もっとも、このような残業禁止の命令は、明確なものである必要がありますので「口頭で残業しないよう指示した」程度の主張ではあまり意味がないでしょう(また、口頭での指示ではこれを立証することも困難です。)。
また、仮に明示的な指示をしていても、従業員が残業をしていることを知りながら又は容易に知り得たのに残業を制止せずに黙認していたような場合にも、会社側の反論はあまり有益ではないと思われます。
このような反論が活きるのは、
- 会社が従業員に対して書面やEmail等の明確な形で残業を禁止することを通知し
- かつ残業行為が行われている場合にはこれを都度制止して注意したり
- 業務を分配して残業をさせないような具体的措置を講じていたような場合
において、従業員が通知や制止を無視して残業を続けていたという限定的なケースに限られるとお考えください。
残業代の消滅時効が完成した
残業代請求権の消滅時効が完成している場合、会社は消滅時効を援用することによって、残業代の支払い義務を免れることができます。
2020年4月1日施行の民法改正に合わせて、残業代請求権の消滅時効期間は2年から3年に変更されました。
そのため、現在の消滅時効期間は以下のとおりです。
|
残業代請求権の発生時期 |
消滅時効期間 |
|
2020年3月31日以前 |
2年 |
|
2020年4月1日以降 |
3年 |
なお、未払いの残業代のうち一部についてのみ消滅時効が完成しているということも考えられます。そのため、どの範囲で未払い残業代が消滅時効にかかっているのかをよく確認しましょう。
労働基準法上の管理監督者に該当する
従業員が「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に該当する場合には、労働基準法上の労働時間規制の多くが適用されません(労働基準法41条2号)。
例えば、管理監督者である従業員については、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払義務は発生しません。そのため、「労働者が管理監督者に該当する」旨の反論が認められれば、従業員側の請求の大部分が棄却される可能性はあります。
ただし、労働基準法の管理監督者に該当するかどうかは経営者と一体的立場に当たるかどうかを職務・職責・待遇等を総合考慮して判断します。そのため、役職的には管理職であっても、直ちに管理監督者に該当することにはなりません。
管理監督者か否かの判断要素としては、以下のような事項があります。
- 経営への参画の程度
- 職務上の権限の程度
- 業務への裁量の程度
- 待遇の優位性の程度
会社としては、上記の観点から実質的に見て、その従業員が管理監督者であるといえることを主張・立証する必要があるため、そのハードルは高いです。
固定残業代を支給している
会社が固定残業代制を適正に導入・運用している場合、会社は定額支給分については残業代の精算をしていることになります。そのため、実際に支払うべき残業代が定額支給分を上回らない限り、会社は追加で残業代を支払う必要はありません。
ただし、固定残業代制を適正に導入・運用するには、以下の要件をすべてみたすことが必要です。
- 通常労働時間に対する賃金と残業時間に対する賃金を明確に区別できること
- 固定残業代が残業行為の対価として支給されていること
また、固定残業代制度はあくまで定額支給の範囲では残業代精算があったものとみなす制度ですので、支払うべき割増賃金額が定額支給分を超えた場合には、超過分については残業代を別途支払う必要があるので注意しましょう。
残業代請求訴訟で会社の言い分が認められた裁判例3選
残業代請求訴訟に関する裁判例で、会社の言い分が認められたものを3つ紹介します。それぞれ具体的な事情に応じて、会社からの反論が奏功した例として、参考にしてください。
蛭浜タクシー事件(福岡地判平成19年4月26日)
タクシー運転手が、所属先のタクシー会社に対して残業代を請求した事件です。
従業員の主張に対してタクシー会社は、従業員が労働基準法上の管理監督者に該当すると反論しました。
裁判所は以下の理由から、従業員が労働基準法上の管理監督者に該当すると判断し、会社の言い分を認めて従業員の残業代の請求を棄却しました。
- 一定の人事に関する決定権を有していたこと
- 出退勤時間が従業員の裁量に任されていたこと
- 従業員の受けている報酬が他の乗務員に比べて高額だったこと
神代学園ミューズ音楽院事件(東京高判平成17年3月30日)
音楽院の従業員8名が、勤務先の音楽院に対して残業代を請求した事件です。
しかしこのケースでは、音楽院側から従業員に対して、朝礼などを通じて繰り返し残業禁止の指示が行われていました。また、所定労働時間の間に業務が終わらない場合には、管理職に残りの業務を引き継ぐように指示が出ていました。
上記の事実を前提として、裁判所は、従業員が音楽院側の明示的な残業禁止の指示に反して残業を行ったものと判断しました。
そのため、従業員の音楽院に対する残業代請求は棄却されました。
富士運輸事件(東京高判平成27年12月24日)
トラックの運転手が、所属している運送会社に対して残業代を請求した事件です。これに対して運送会社は、固定残業代を支払っているため未払い残業代はないと主張しました。
裁判所は以下の点を重視して、未払い残業代はないと判断しました。
- 就業規則に固定残業時間制を採ることが明記されていた
- 就業規則は従業員の誰もが閲覧可能な状態にあった
- 実際の残業時間に相当する額以上の固定残業代が支払われていた
従業員からの残業代請求への対応を弁護士に依頼するメリット
従業員から未払い残業代を請求された場合、弁護士に依頼することを強くおすすめします。
従業員からの残業代請求への対応を弁護士に依頼することにはさまざまなメリットがありますので、以下でその一部を紹介します。
法的に漏れのない訴訟準備が可能
弁護士は法律の専門家ですので、会社側として未払い残業代の支払い義務を争うためのポイントを熟知しています。
そのため、労働者が繰り出してくる主張に対して適切な反論を検討し、訴訟に向けて漏れのない準備をすることが可能です。
訴訟準備に必要なマンパワーを確保できる
残業代請求訴訟に対応するためには、反論内容の検討や書類の作成に膨大な手間がかかります。
会社によっては法務部内に弁護士を抱えている場合もありますが、法務部のメンバーだけで訴訟の準備をするのは、マンパワーの問題から現実的に困難です。
この点、残業代請求訴訟の対応を外部弁護士に依頼すれば、マンパワーを確保して充実した訴訟準備を行うことが可能になります。
従業員側に弁護士が付いている場合も安心
もともと会社と従業員の間には、マンパワー・経済面・知識などの点で大きな力の差があります。しかし、従業員側に弁護士が付いている場合は、この力の差は大きく縮まると考えて良いでしょう。その際には、会社側も弁護士を付けることによって、従業員側と対等以上に渡り合うことが可能です。
労務一般についてのアドバイスも受けられる
従業員から未払い残業代の請求を受けた場面に限らず、労務に強い弁護士と普段から繋がりを持っておくことも、会社にとってはメリットが大きいといえます。
会社側の労務に強い弁護士と顧問契約を締結しておけば、会社の中で日常的に発生する労務問題一般についてのアドバイスを受けることもでき、会社としての労務管理体制が安定することとなるでしょう。
まとめ
従業員からの残業代請求を受けた場合、会社は請求に応じるかどうかの検討を含めて、戦略的に準備をする必要があります。
会社としては、会社側の労務に強い弁護士と協力して、慎重に対応を検討すべきです。
また、会社を経営するにあたっては、労務問題は避けては通れない途です。
そのため、日常的に労務問題について相談できる弁護士と繋がりを持っておくことも、会社にとっては有益でしょう。
従業員から未払い残業代を請求されて困っている、またはまた日常的に労務問題に関して相談できる専門家との繋がりがほしいという会社担当者の方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士に問い合わせる