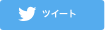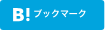従業員を雇うとき、企業は従業員と雇用契約を締結するでしょう。
最近ではその際に試用期間を設ける企業が多くなりました。
しかし、試用期間について曖昧に認識していたことで、後にトラブルになってしまうケースも発生しています。
試用期間とは何か、本採用との違いは何かについてご説明します。
加えて、後々トラブルが起きないように雇用契約書の必要性や、いつ雇用契約を交わすのか、記載しておくべき内容などをご紹介していきます。
弁護士に問い合わせる
試用期間でも雇用契約書は必要か
たまに試用期間中は雇用契約書を作成しないという企業もありますが、そもそも雇用契約書を作成する義務は企業にはありません。
ですが、その必要性はとても高いものです。
雇用契約における試用期間とは
企業が新しく人を採用するときに、書類や面接だけではその人のスキルや勤務態度を判断するのが難しい場合があります。
その際に、一定期間を設けて本採用するかを判断する期間のことを試用期間と言います。
法的な決まりはない
試用期間という制度は法律で定められている制度ではありません。
ですが、最高裁の判例で試用期間のことを『解約権留保付の雇用契約』という形で認める判例が出ています。
『解約権留保付の雇用契約』というのはすなわち、試用期間中に無断欠勤が続いたり、勤務態度が悪かったり、能力面で適正がないと判断された時に雇用契約を解約することができる権利ということになります。
試用期間かどうかに関係なく雇用契約書は結んでおくことがおすすめ
『雇用契約書を交わさないといけない』という法律はなく、企業にとって雇用契約を交わすことは義務ではありません。
ですが、書面として記載しないといけない事項が法律で決められているので、雇用契約書や雇用通知書といった書面を交わすのが一般的となっています。
また、雇用契約書は労働者と使用者が双方に労働条件などに関して納得をして捺印するもの。
試用期間であっても後々のトラブルを避けるために、合意をした旨を契約書として残しておくのがおすすめです。
有期雇用契約
企業が人を雇用するときは、期限を設けないで雇用契約をするのが一般的ですが、試用期間の意味合いで期限を設けて雇用契約をする企業もあるそうです。
その期限は3ヶ月、6ヶ月、1年といった期間が多いようです。
雇用契約はいつ締結する|雇用契約を結ぶタイミング
雇用契約は通常は入社前か初出勤日に交わします。
すなわち、内定から入社日までに交わすのが一般的です。
入社初日が一般的
多くの企業は入社日に雇用契約を締結します。
出社して契約書を交わしてから勤務スタートです。
締結がない・遅いとトラブルになるケースも
たまに雇用契約書を作成しない企業や、入社して日数が経ってから契約を交わすケースがあります。
そういった場合、後に契約内容・労働条件について企業と労働者側で認識の違いなどが生まれ、トラブルになってしまうケースがあります。
口頭でも雇用契約は成立しますが、労働時間や給与の条件等で双方の認識の違いがないように書面を交わすことはとても重要です。
雇用契約がないことによるトラブルの例
当サイトの『法律相談Q&A』にも雇用契約書に関するトラブルについて、多数質問が寄せられています。
今の会社に勤めて3年になります。今まで雇用契約書を渡された事がないのですが、雇用契約書にサインが欲しいと言われました。
が、内容は労働者の不利になる内容です。 勤務時間の20分前に来て、掃除をしているにも関わらずその事は書いてありません。そしてその賃金は1度も支払われた事がありません。
私は時給1500円貰っていますが、それは3年前からずっとその契約で働いて来ています。
新たな契約書には時給1200超えた賃金に関しては残業代、深夜手当として含む。と記載されています。
確かに、働き初めた時に雇用契約書などはなく、サインもしていないので1500円契約+残業代という契約書はありません。
が、私以外にも1500円で働いてる子達は沢山いますので証言は出来ると思います。
この新しい雇用契約書にサインしたくありません。拒否する権利はあるのでしょうか?また、拒否して解雇された場合は解雇手当(1ヶ月分の賃金)以上に請求出来ますでしょうか?
この件に関して、弁護士は、「雇用契約書を拒否することで、不当な扱いを受けるなどした場合、法的に争うことができるので、同じ扱いをされた人たちと集団訴訟をしてみては。」と回答しています。
試用期間中の雇用契約で記載すべきき4つのこと
こうした口頭でのやり取りだとお互いに認識の違いが出てきてしまうことが多いです。
書面にて契約をすることでこうしたトラブルは回避できます。
雇用契約書等で労働条件を提示する際に、必ず記載しないと行けない事項が労働基準法第15条(労働条件の明示)で定められています。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
引用元:労働基準法第15条
試用期間がいつまでか
有期雇用契約の形で試用期間を設ける場合は、雇用期間がいつからいつまでということを記載しないといけません。
(契約期間等)
第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
引用元:労働基準法第14条
本採用に至る条件
試用期間が終了したあとは、特段な事由がない限り雇用を継続しないといけないと労働契約法第16条で定められています。
試用期間が終わり本採用するのが前提ですから、逆に本採用しない条件や事由を明示しないといけません。
例えば、無断欠勤が多い、出勤率が90%に満たない、勤務態度が不良などという事由があれば本採用はしないと明記しないといけません。
(賠償予定の禁止
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
引用元:労働基準法第16条
試用期間中の給与ついて
給与については、時給・日給・月給か、締め日や支払日、支払い方法等を明記する必要があります。
解雇に関して
どのような時に解雇されることがあるか明記しないといけません。
また、解雇にも『普通解雇』、『整理解雇』、『懲戒解雇』とあります。
そのそれぞれの事由について明確に記載する必要があります。
雇用契約書の例

試用期間が過ぎた後
試用期間が過ぎた後は、既出の通り特段の事由がない限り雇用を継続することになります。
本採用する場合
試用期間終了後にそのまま本採用する場合は、会社からの辞令があれば本採用となります。
本採用しない場合
雇用を継続させるのが前提ですが、仮に継続させない(解雇)という場合には、継続させない旨やその事由について通知させないといけません。
試用期間の延長も可能
試用期間が終わった後には本採用するかしないか判断するのが一般的ですが、再度試用期間を延長させることもできます。
そのためには、雇用契約書に試用期間を延長する場合がある旨を記載すること、期間を延長させる合理的な事由があることが必要です。
また、延長させる期間は当初の試用期間と合わせて1年以内であるべきです。
試用期間の限度は法律で定められているわけではありませんが、民法90条『公序良俗』の観点から1年以内が限度と考えられています。
まとめ
企業としては優秀な人材を採用したいと考えるものです。
雇用される側も良い企業に勤めたいと考えるものです。
そのために試用期間制度をうまく利用するのも1つの手です。
しかし、その試用期間に関する雇用契約のことでトラブルにならないためにも、しっかりと雇用契約を交わして双方の認識の違いが生まれないようにしていきましょう。
弁護士に問い合わせる