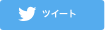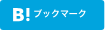知的財産(ちてきざいさん)とは、人間の知的な創作活動によって生み出された経済的価値のあるものの総称です。
知的財産と聞くと、一見して小難しい印象を受けるかもしれません。しかし、私たちの身の回りには、知的活動によって生み出されたアイデアや創作物が満ち溢れています。 その多くは財産的な価値をもつ一方、近年では、知的財産にかかわるトラブルが多く発生しているのも実情です。
この記事では、知的財産の財産的価値を正しく知るとともに、知的財産を活用するために理解しておきたい知的財産権についてもご紹介します。
知的財産の種類や価値
まずは、知的財産には具体的にどういったものがあり、どのような価値が認められているのか、その全体像を解説していきます。特許庁のHPにも説明が掲載されていますので、ご参照ください。
知的財産の種類|知的活動で生み出されたアイデアや創作物
人の知恵によって生み出されたアイデアや創作物には、主に以下のようなものがあります。
著作物
著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいいます。具体的には、小説・漫画・アニメ・絵画・彫刻・音楽・写真・映画などが該当します。
発明
発明といえば、トーマス・エジソンを連想する人も多いのではないでしょうか。現在では当たり前となったエジソンの発明品「白熱電球」や「発電機」ですが、当時としては非常に画期的で思いもよらないようなアイデア・創作物でした。 特許法では、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のもの」と定義し、特許発明として保護しています。
考案
日用品等の構造や形状を工夫して、より便利なものにした場合、これらは「考案」と呼ばれます。実用新案法では、こうした考案を「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義し、保護しています。
工業デザイン
自動車・ペットボトルの形状やスマートフォンの画面デザインなど、製品のデザインの良し悪しは製品の売れ行きを左右します。そのため、経済的価値を有するものとして、意匠法において「意匠」として保護を受けることができます。
ロゴ・マーク
私たちが日常的に購入している商品には、「商品名」や商品を提供している製造業者の「ロゴ・マーク」が記載されています。このようなロゴ・マークも、商品や会社の「信用」を表すものとして財産的な価値を有するため、商標法で「商標」として保護を受けることができます。
参考:特許庁|商標制度の概要
財産としての価値
知的財産は、有体物ではありませんが、形のない無体財産として財産的価値を有します。
無体財産の特徴として、そのアイデアや技術を知った他人に簡単に模倣されてしまうというものがあります。
たくさんのお金と労力を使って完成させた著作物・技術・デザインを、いとも簡単にマネされてしまう。これでは努力が水の泡となるだけでなく、これまでに費やした投資を回収できず大赤字になってしまう可能性もあります。
したがって、知的財産をどのように管理・活用していくのかは、慎重に見極めていく必要があります。
経済戦略の要素
知的財産のどのように管理・活用していくのかを考えることは、知財戦略とも呼ばれています。
特許権や商標権など知的財産に関する権利を取得していくのか、しないのか。 権利を取得する場合、どのようなタイミングで取得するのか、どのくらいの範囲で権利を取得していくのかをケースバイケースで考えていかなければなりません。
また、権利を取得しない場合、重要な技術やアイデアは秘密の状態で管理し続けることが必要です。
このように、知財戦略は経営戦略と結びついたものであるといえるでしょう。
知的財産権
知的財産の中には、特許権や著作権など法律で規定された権利として保護されるものがあり、これらの権利を総称して「知的財産権」といいます。 知的財産権は、大まかに3種類に大別されます。
著作権
小説や音楽、絵画など「著作物」を創作したときに発生する権利を著作権といいます。
著作権は、さまざまな種類の権利の束であり、これを支分権といいます。 代表的なものとして、著作物を複製する権利である「複製権」、公衆に著作物を見聞きさせる「上演権」「演奏権」、インターネット等で公に伝達する「公衆送信権」などがあります。
産業財産権
産業財産権は、文字通り産業に関する権利をいい、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4種類の権利を総称したものです。
詳しくは後述しますが、いずれも共通して、自然に発生する権利ではなく、特許庁に必要書類をまとめて出願をする必要があるという特徴があります。なお、登録されると、一定期間、そのアイデアや創作物を独占的に利用することが法律で認められます。
その他
著作権や産業財産権のほか、回路配置利用権や育成者権、地理的表示(GI)、肖像権、パブリシティ権などがあります。
産業財産権の種類
産業財産権は、以下の4つに分類されます。
特許権
特許権とは、現状の問題点を解決する技術的アイデアを創作した者に与えられる独占排他権をいいます。
特許が付与された発明を特許発明といい、特許を受けることで原則として出願から20年間、その特許発明を独占的に利用することが認められます。
なお、特許を受けるためには特許庁による審査を受け、新規性・進歩性・産業場利用可能性など一定の要件を満たしていることが求められます。
実用新案権
実用新案権は、物品の形状、構造または組み合わせに係る考案を保護するための権利をいいます。
発明ほど高度な技術的アイデアではない小発明は、実用新案権として出願から10年間保護を受けることができます。
実用新案権は、実体的な審査を経ず、早期に権利化することがきるため、ライフサイクルの短い技術に対して有効です。
意匠権
意匠権とは、物品の特徴的なデザイン(形状・模様など)に対して与えられる独占排他権をいいます。
物品全体のデザインだけでなく、物品の部分に特徴のあるデザイン、画面のデザイン等も登録から20年間保護されるのが特徴です。
意匠権の効力は同一の範囲のみならず、登録されたデザインの「類似の範囲」にまで及ぶため、第三者による模倣品の流通を防止することができます。
商標権
商標権とは、商品・サービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権をいいます。
権利の存続期間は10年間と特許権や意匠権より短いですが、更新することで、20年、30年と継続的に保護を受けることができます。
また、原則として出願時に指定した商品・サービスと同一・類似の範囲で効力を有します。著名な商標は、「防護商標登録」を受けることで、非類似の商品・サービスについても第三者による使用を排除することができます。
その他の知的財産権
著作権や産業財産権以外にも、いくつか知的財産権があります。
回路配置利用権
あまり一般には知られていませんが、半導体集積回路配置法という法律があります。
回路配置利用権とは、半導体の集積回路(レイアウト)を創作した者に与えられる権利のことです。
この法律を利用することで、特許法や意匠法で保護を受けることができない回路配置についても、新たに開発された回路配置の無断模倣を防止することができます。
育成者権
育成者権とは、野菜や果物など新たに品種改良をして生み出された新品種を保護するものをいい、種苗法という法律により保護されています。育成者権の存続期間は品種登録された時期により異なりますが、2018年現在の存続期間は25年間(永年性植物は30年)であり、品種登録手続きを行う必要があります。
出典:種苗法第十九条
知的財産を活用するために
知的財産の活用方法として代表的なのが、特許権・実用新案権・意匠権・商標権等の取得です。
権利化を図ることで、登録が認められたものについては独占的に使用すること法律で認められ、第三者による無断模倣等に対して権利行使をすることができるようになります。
ただし、登録にはそれぞれ要件が課せられるため、所定の要件を満たした出願をしなければなりません。
特許(実用新案)を取得する
開発した発明・考案は、そのままでは保護が認められません。保護を受けるには、まずは特許法・実用新案法で規定された手続きを踏む必要があります。
なお、たとえ日本で特許を取得し独占排他的な利用が認められたとしても、そのままでは日本以外の国で特許権の権利行使をすることができません。
日本の法律は日本国内でのみ効力が及ぶように、日本の特許法・実用新案法の効力も海外では及ばないからです。
欧州や中国、韓国など他国でも特許権を取得したい場合は、それぞれの国ごとに特許出願を行うか、特許協力条約に基づく国際出願を行なってから権利化を望む国々に手続きを移行していくかの、どちらかを選ぶことになります。
取得はほぼ特許庁にて
日本で特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得する場合は、日本の特許庁で手続きを行います。
特許権を取得するための手続きの流れは、以下の通りです。
特許出願
日本では、一番先に特許出願をした者に特許権を与える「先願主義」を採用しています。したがって発明品が完成したまま放置してしまうと、他人に特許権を取られてしまうというリスクがあります。開発に成功したら速やかに特許出願をすることが望ましいでしょう。
また、特許要件の1つである「新規性」を失わないために、特許出願前は、他人に発明の内容を知られないようにしておかなければならないことにも留意してください。
出願公開
出願から1年6ヶ月が経過すると、出願当初の特許出願の内容が公開されます。
現行の特許法では、原則として、特許出願された発明はすべて、特許庁の発行する特許公開公報に掲載されることになっています。
審査請求
特許を取得するには、出願日から3年以内に審査請求を行います。
審査請求をせずに3年以上放置してしまうと、出願は取り下げられたものとみなされるため、権利を取得したい場合は必ず審査請求を行います。
ただし、実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願では、審査請求に関する規定がないため、これを行う必要はありません。
方式審査
審査請求されると、まずは出願書類が特許法で規定された様式に則り記載されているかどうかが審査されます。 書類に不備がある場合は、補正を行います。
実体審査
方式審査をパスすると、出願された発明に、特許権を与えてよいものかどうか審査されます。
特許権を与えることができないと判断された場合、出願人に「拒絶理由」が通知されます。
拒絶理由通知を受け取った出願人は、意見書の提出や、出願内容の補正をする機会が与えられ、再度審査を求めることができます。
特許査定
審査の結果、意見書や補正によって拒絶理由が解消した場合は、特許査定となります。
出願人は、特許査定があった後、所定の期間内に特許料を支払うことによって、特許原簿へ登録されて特許権が発生します。
その後、しばらくすると特許掲載公報に特許発明の内容が掲載されます。
参考:制度・手続(特許庁)
どれが適切かは弁護士などに相談
知的財産の中でも、どの法律を利用することで権利を取得できるのかどうかは、個々のケースにより異なります。
さらに、権利を取得するタイミングや、取得する権利の範囲、要件を満たすためにどのような対策をすべきかについても、あらかじめ検討しておかなければなりません。
これらの判断には、知的財産に関する高度な専門知識を必要とするため、知的財産に精通した弁護士や弁理士からのアドバイスを受けることをおすすめします。
まとめ|知的財産を守ることが、事業成長につながる
近年、特許を取得する予定だった製品が同業他社に先に取られてしまう、自社で用いるはずだった名称やロゴ・マークが、同業他社に商標登録されてしまい、使用することができないなどのトラブルが多く発生しています。
このようなトラブルを未然に防ぐためには、知的財産に関する正しい知識を持ち、知的財産権を上手く取り扱っていくための戦略を、しっかりと立てていくことが第一歩です。
そして、こうした綿密な知財戦略は結果として、順調な事業成長へとつながっていくでしょう。
| 出典元一覧 |