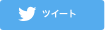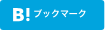コンプライアンスとは企業が法律(法令)や倫理に背かず守る(遵守する)ことを指します。
企業内の風紀や社会的信頼のためにも1人1人が守るべきものですが、違反事例は後を絶たず、株式会社東京商工リサーチによると2017年4月〜2018年3月の間でコンプライアンス違反がきっかけで倒産に至った会社は、実に231件と発表されています。 (参考:TDB)
この記事では実際に起きた事例を用いて、コンプライアンス違反について紹介します。また原因をご紹介しますので、しっかり遵守できているか判断する際の参考にしてみてください。
【PR】コーポレートガバナンス強化の為、社外取締役に弁護士の起用を考えている企業様へ
IPO経験者、上場企業の役員経験がある弁護士をご紹介します。
URL:https://outside.no-limit.careers/
リスク管理と実践的対応策
「うちは中小企業だから大丈夫」は大きな誤解。
法令違反や内部不正が起これば、行政処分・取引停止・信用失墜で経営に致命的なダメージを与えかねません。
弁護士監修の本資料では、
● 中小企業が直面しやすい主要リスクと最新法令のポイント
● 社内規程・教育・内部通報制度を連動させた実践的フレームワーク
● 社内規程・教育・内部通報制度を連動させた実践的フレームワーク
を実務的な観点から解説。
今すぐ無料でダウンロードして、
組織を守るコンプライアンス体制を強化!
コンプライアンス違反した9の事例
実際にどのようなコンプライアンス違反が発生しているのか、9の項目に分けて事例を紹介します。
事例1:労働問題

企業の労働問題もコンプライアンス違反に該当します。代表的な例として、セクハラ・パワハラなどです。この他にも、残業代未払い、賃金未払い、不当解雇なども挙げられます。
セクハラでコンプライアンス違法したケース
2016年の調査では、寄せられた相談の35%以上がセクハラに関する問題です。セクハラは業界を問わず発生しており、最近の大きな報道では大手企業の社員がOB訪問において性的暴行を行ったとして逮捕起訴されました。
パワハラでコンプライアンス違反したケース
人格を否定するような発言や、暴言によって相手を脅す行為、明らかに不要な業務の押し付け、過剰(過少)業務の押し付け等はパワハラに該当します。
複数の上司によるパワハラが原因で退職に追い込まれたとして、元陸上自衛官が国に損害賠償を請求した事例もあります。地方裁判所は、退職の原因が上司の常識の範囲を逸脱した指導や暴行であると認め、100万円の損害賠償を認めました。
残業代未払いでコンプライアンス違反したケース
残業代未払いも会社のコンプライアンス違反に該当します。全国の労働基準監査署では、2016年4月から2017年3月までの間に1,349企業に対し、合計127憶2,327万円を支払うよう指導しました。
近年、宅配業者や携帯会社、電気会社などさまざまな業界の大手企業で、次々と残業代の未払いが発覚しております。
大手宅配業者では「博多北支店」において、2016年6月から7月にかけての従業員の労働時間管理を適正に行っておらず、労働基準法違反に該当するとし、本社と「博多北支店」の幹部2人が、福岡地方検察庁に書類送検されました。
事例2:不正受給

不正受給とは、働いたことを申告しない、偽った申告をすることで国からの助成金・補助金を不正に受給することです。コンプライアンス違反になる企業の不正受給には「診療(介護)報酬不正受給」や「助成金不正受給」などがあります。
診療報酬を不正受給したケース
熊本県玉名市の病院では、勤務時間を偽装し2015年4月から合計8,000万円以上の診療報酬を不正受給していたことが2019年1月23日に発覚し、不正受給分の返還処分になりました(参考:毎日新聞)。
キャリアアップ助成金を不正受給したケース
企業内の非正規雇用者の人材育成に取り組んだ事業主を助成するための制度に、厚生労働省の管轄する「キャリアアップ助成金」があります。
兵庫県の労働基準監督署の非常勤職員が、実際には雇用していない人物名でキャリアアップ助成金を申請し、合計1,200万円の助成金をだまし取ったとして、懲戒処分を受けました(参考:神戸新聞NEXT)。
事例3:粉飾決算等不正会計

粉飾決算とは、不正な会計処理によって、故意に賃借対照表や損益計算書、決算書を操作し、企業の財務状況や経営状況が悪化しているにも関わらず、黒字として監査に提出するといった違法行為です。2017年度では、コンプライアンス違反で倒産した企業231件中、72件は粉飾決算が原因とされています。
| 最新の事例では、上場企業であるバイオ燃料会社が2017年3月期決算において、キャッシュフローがマイナス約9憶6,000万円にも関わらず、プラス1憶3,000万円と偽り報告書を提出したとして、実質経営者が3人起訴される事件が発生しました(参考:Yahoo!ニュース)。 |
この他にも、有名なアニメ制作会社や振袖販売・レンタル会社などさまざまな業界の企業に粉飾決算等不正会計の容疑がかけられています。
粉飾決算をする理由は、融資の継続・各機関や株主への体裁の維持・上場維持などさまざまです。粉飾決算を社長が実行したり指示したりした場合、「特別背任罪(会社法960条)」に問われる可能性があり、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこれらの両方が科せられる可能性があります。
事例4:個人情報流出

個人情報流出とは、その名の通り企業が管理する顧客情報等が情報セキュリティの不備等により、流出してしまうことを指します。大きな漏洩事件以外、あまり耳に入りませんが、2017年の発生件数は386件、漏洩人数は519万8,142人と多くの被害が出ています。
| 最近の大きな事例では、2019年の3月29日に大手自動車会社のネットワークに、外部からの不正アクセスが確認され、最大310万件の顧客情報が流出した可能性があることが発表されました。ハッキングされていたため警察が調査を進めています(参考:読売新聞オンライン)。 |
個人情報漏洩は、起業の大きさに関係なく発生するリスクがあります。個人情報漏洩は会社的な信用に響きますし、金銭的損害に直結する情報が漏洩してしまった場合、多額の損害賠償を支払う事件に発生してしまうでしょう。
事例5:偽造事件

偽造とは、本来作成権限がないのにも関わらず、他人名義で書類を作成し、あたかも正式な書類であったかのように作成することです。刑法上の偽造には、「通貨偽造罪」や「有価証券偽造罪」「文書偽造罪」などが挙げられます。
|
最近注目を集めた偽造による事例としては、「森友学園」への国有地売却問題でしょう。森友学園への国有地売却をめぐり、財務省幹部らが背任、および「虚偽文書作成」等の罪で告発された事件になります。 |
結論としては、森友学園への国有地の大幅値下げ売却に関する背任や、虚偽有印公文書作成等で告発されていた前理財局長をはじめとする38人全員が不起訴処分となりました(参考:Business Journal)。
事例6:食品の衛生管理

飲食業界や食品製造業界に従事する場合、食品の衛生管理もコンプライアンスに含まれます。食品の衛生管理を怠りコンプライアンスをおろそかにするとお客の健康状態を害し、死に直結するリスクも高まるでしょう。
| 食品衛生管理を含めた問題で、多くの注目を集めた事例には、2017年8月に埼玉県・群馬県の両県のお惣菜店を利用した客が、腸管出血性大腸菌O157に感染し1人が死亡した集団食中毒を引き起こした例があります(参考:日本経済新聞)。 |
具体的な食中毒への感染経路は判明しませんでしたが、売り場では「客の使用するトングを交換してしなかった」「調理担当の店員が手袋をつけたまま会計をしていた」などリスク管理に不足部分があったようです。
当該惣菜店は、「感染源が特定されていない中で営業再開は難しい」とし、同年9月20日に全17店舗を閉店することになりました。
事例7:著作権侵害

著作権とは、著作者がその著作物について、保護期間内において、独占的に、複製・翻訳・翻案などを行える権利のことです。
著作権侵害とは、無断で著作物をコピーする「複製権の侵害」をはじめ、「上演権や演奏権の侵害」「上映権の侵害」「公衆送信権・公の伝達権の侵害」などの行為が該当します。
| 2017年2月、他人がインターネット上で公開していた風景写真を無断で複製し、複製権の侵害を行なった上、1冊5,000円の写真集を販売したとして、長野県警は著作権法違反の疑いで東京都の団体職員の男性を逮捕しました(参考:産経ニュース)。 |
著作権を侵害した場合には、「差止請求」や「損害賠償請求」「不当利得返還請求」「名誉回復などの措置」が課せられることになります。
事例8:景品表示法違反

景品表示法違反とは、「不当景品類及び不当表示防止法」のことを指し、過大な景品付販売や誇大広告、不正表示等により消費者を惑わす販売行為を防止する目的で制定されています。
景品表示法違反で多くの注目を浴びたのは、2016年4月に大手自動車メーカーが公表した燃費試験データに不正があった事例です。
| 実際の燃費が販売用のカタログ値を下回っているにも関わらず、それを上回る数値を提示したことに対し、消費者庁は、実際の燃費とまるでかけ離れた数値を広告したことは「景品表示法違反」に該当するとして、4億8千万円程度の課徴金納付を命じました(参考:日本経済新聞)。 |
広告のキャッチコピーなどは、特に注意が必要です。
事例9:出資法違反

出資法とは、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と呼ばれるもので、以下のようなことを制限しています。
|
事例として、以下のようなものがあります。
|
仙台の貸金業者が、借用証明書を交付せず、出資法で定められている制限利息の9倍や10倍の利息で貸し付けを行った疑いで、経営者を含む3名を逮捕した事例です(参考:河北新報) |
リスク管理と実践的対応策
「うちは中小企業だから大丈夫」は大きな誤解。
法令違反や内部不正が起これば、行政処分・取引停止・信用失墜で経営に致命的なダメージを与えかねません。
弁護士監修の本資料では、
● 中小企業が直面しやすい主要リスクと最新法令のポイント
● 社内規程・教育・内部通報制度を連動させた実践的フレームワーク
● 社内規程・教育・内部通報制度を連動させた実践的フレームワーク
を実務的な観点から解説。
今すぐ無料でダウンロードして、
組織を守るコンプライアンス体制を強化!
コンプライアンス違反につながる3つの原因
コンプライアンス違反に至る原因はさまざまですが、アメリカの犯罪学者であるD.R.クレッシーは不正行為が発生する仕組みについて下図のような「不正のトライアングルの理論」を唱えました。

「動機」「機会」「正当化」の3つの条件がそろった時、コンプライアンス違反が起きると考えられます。具体例とともに、ご紹介します。
動機|相談窓口の設置などケア体制の不備
不法行為を行う原因はさまざまですが、個人的な動機がなければ基本的にコンプライアンス違反は起きません。例えば、事例で紹介したような粉飾決算等不正会計では、「融資を受け続けたかった(できるだけお金が欲しい)」などの動機があったと思われます。
特に金銭的な問題を抱えている従業員は、不正受給などの金銭に関するコンプライアンス違反に走りやすいといえます。社内に従業員が相談できる相談窓口の設置や相談できる外部窓口の設置が必要です。
顧問弁護士を法律相談窓口として設置し、従業員が相談できるようにするのもひとつの方法です。
機会|不正行為が発生しやすい職場環境
機会とは、不法行為をしやすい職場環境などを指します。例えば、長時間の無休労働を強いる会社では、授業員にもストレスが溜まり、些細なことで部下を過剰に叱りつける問題が発生しやすくなるでしょう。
他にも、権限が1人に集中している場合や、印鑑が菅理されておらず誰でも押印できる場合など、不正を行いやすい職場環境といえます。体制を見直し、コンプライアンス違反が起きにくい職場環境にしなければなりません。
正当化|認識・危機意識が低い
多くの人は、不正を考えても良心や理性が最終的なブレーキとなり、実行しません。「正当化」とは、その不正をすることが正しいかのように、理由や言い訳をつけ、実行してしまうことです。
これは、不正を行う人のコンプライアンス違反に対する認識や危機意識が低いことが原因でもあります。まず、不正行為を行ったらどうなるのか、自社ではどのような対応を行うのかを認識させることは重要でしょう。
従業員がコンプライアンス違反した場合の対処法

従業員がコンプライアンス違反した場合の対処法についてご紹介します。
早急に発生原因や動機、被害状況を確認する
従業員がコンプライアンス違反をした場合には、その発生原因や動機、被害状況を迅速に特定しなければなりません。
発生原因等を特定するためには、社内における通報窓口や、内部委員会の設置など、事前にコンプライアンス専門部署を検討しておく必要があります。
コンプライアンス違反が起きてから「どのように動けば良いのかわからない」では、被害が拡大してしまう可能性があります。事前に専門部署を設置して、迅速に対応できるようにしておきましょう。
弁護士にどのように対応していくべきか確認する
従業員によるコンプライアンス違反が発生したら、今後どのような対応をすれば良いのか事前に弁護士に確認しておきましょう。必要によっては、顧客への謝罪、示談や裁判の準備、報道や関係者などへの報告などを行わなくてはなりません。
当該従業員の法的対応の有無や、処分内容についても法的にどのような対応ができるのか確認する必要があるでしょう。これらをスムーズに対応できるよう弁護士に相談しましょう。
当事者・関係者の処分を検討する
コンプライアンス違反をした従業員に対しては、その被害の程度や状況により法的な対応や、然るべき処分を決定しなければなりません。
こちらも企業法務に詳しい弁護士と相談の上、当事者やその関係者の処分を行うようにしましょう。
状況がまとまったらメディア等へ隠さず報告する
コンプライアンス違反が発生した場合には、今後の企業透明性を確保するためにも、包み隠さずきちんと公表・報告すべきでしょう。社会的な信用の失墜を懸念するかと思いますが、隠しておいて後から知られた場合の方が、多くの社会的信用を失います。
外部だけでなく内部従業員に対しても、会社としてどのような対応を取るのかを明確にする必要があります。会社の対応が後手に回ってしまうと、従業員からの信頼も失墜する形になりかねません。事前に策定したフローにそって、迅速な対応をしましょう。
会社全体で従業員の再教育を行う
従業員によるコンプライアンス違反が発生した場合でも、そうでない場合でも会社全体でコンプライアンス教育を再徹底する必要があります。
従業員に徹底したつもりでも、定期的に再教育をしなければコンプライアンスが乱れる要因につながります。
従業員のコンプライアンス再教育にあたっては、コンプライアンス問題に詳しい弁護士のサポート受けましょう。
リスク管理と実践的対応策
「うちは中小企業だから大丈夫」は大きな誤解。
法令違反や内部不正が起これば、行政処分・取引停止・信用失墜で経営に致命的なダメージを与えかねません。
弁護士監修の本資料では、
● 中小企業が直面しやすい主要リスクと最新法令のポイント
● 社内規程・教育・内部通報制度を連動させた実践的フレームワーク
● 社内規程・教育・内部通報制度を連動させた実践的フレームワーク
を実務的な観点から解説。
今すぐ無料でダウンロードして、
組織を守るコンプライアンス体制を強化!
コンプライアンス違反の事例から考えられる予防対策とは
ここでは、コンプライアンス違反の事例から考える予防対策について詳しくご紹介させていただきます。
自社のリスクを再確認する
コンプライアンス違反を引きおこさないためには、社内ヒヤリハット事例や、過去にコンプライアンス違反がある場合には、その事例を徹底検証し、自社に起こり得るリスクを徹底検証する必要があります。
業界ごとに関係する法律も異なりますので、自社業界に経験のある弁護士にリスクチェックをしてもらうことをおすすめします。小さなリスクの見落としは、大きなトラブルに繋がる可能性もあります。徹底したリスク管理が重要です。
最低限抑えておくべき法律が何か弁護士に相談する
企業の形態によって、最低限抑えるべき法律が異なります。これは業態による違いも関係するため、事前に重要な法律は顧問弁護士や法律の専門家に確認しておきましょう。
会社の経営陣が率先して、コンプライアンスに関する理解を深めることが非常に大切です。
コンプライアンス研修で従業員に危機感を持ってもらう
コンプライアンス研修は、定期的に行うことが推奨されます。
役職や部署ごとに異なる行動規範を含めたルールの確認、コンプライアンス違反をするとその後どのような影響を及ぼすのかも含めて、コンプライアンスに詳しい専門家を招き危機感をもって学ぶことが重要です。
まとめ
一口にコンプライアンス違反といっても、今回ご紹介した事例のようにさまざまな要因があります。
まずは、自社に関係する最低限のコンプライアンス規範を確認し、定期的にコンプライアンスについての教育を強化する、企業法務に詳しい弁護士と顧問契約をし、コンプライアンスへの対応を強化するなど対策を講じていきましょう。
弁護士に問い合わせる